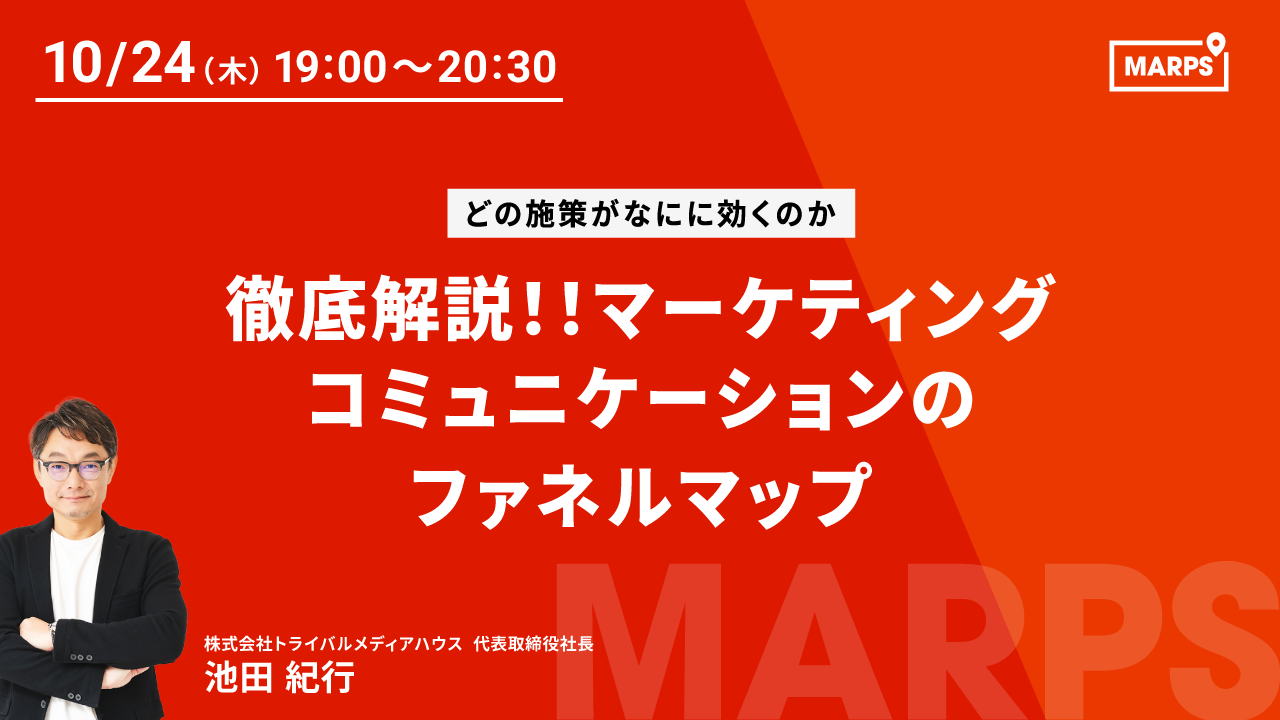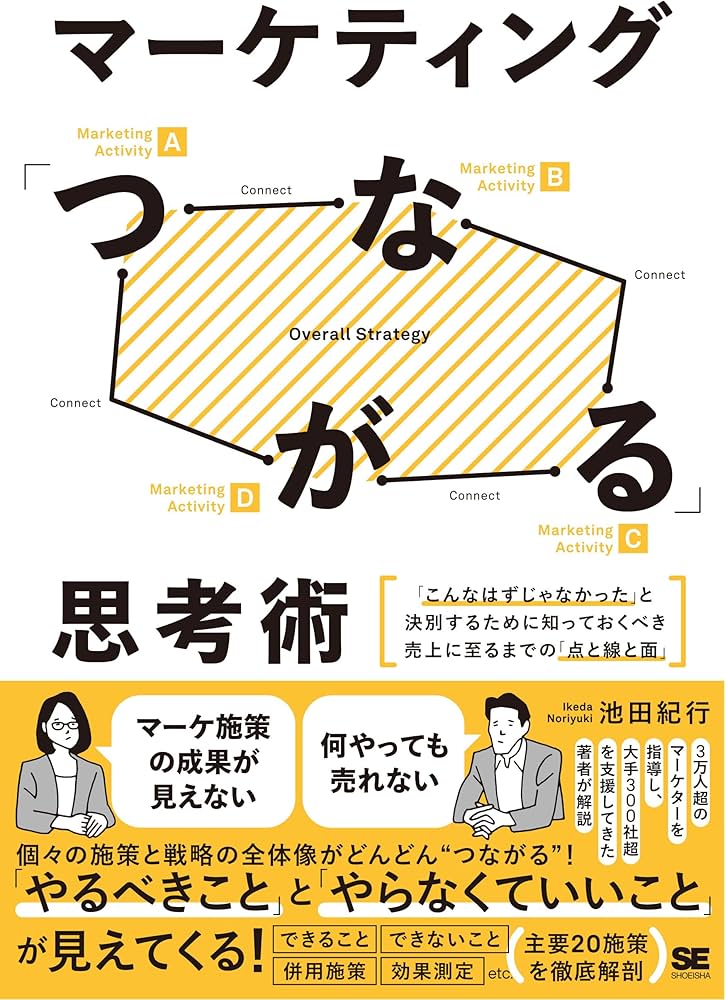1. はじめに:前回の復習と本日のテーマ
前回講義「売上の地図」の振り返り
皆さん、こんばんは。今週も始まりました木曜日のMARPSでございます。今日は先週に引き続き、マーケティングコミュニケーションのファネルマップ、要はPESOの徹底復習大会の回になっております。
先週は2回連続講義の1回目ということで、この「売上の地図」について徹底解説をしました。こちらの1から5、商品カテゴリーマトリックスや「今すぐ客」「そのうち客」、そして売上の地図の中でも最も重要な、売上に影響を与えている1つ手前の重要変数としてのメンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティ、そしてブランドカテゴライゼーションです。
メンタルアベイラビリティ、つまりニーズが顕在化した時に一番最初に思い出してもらうポジションを獲得するためには、想起集合や第一想起を獲得する必要があります。それを説明している枠組みとしてブランドの復習をし、この想起を高めるために、結局想起も出力ですから、この出力としての想起を上げるための入力はプリファレンスを上げる必要があって、このプリファレンスは「価格」「ブランドエクイティ」「製品パフォーマンス」の3つによって成り立っています。
という全体的な売上の地図の構造について学んだのが前回で、今日はこの続き、6、7、8を学んでいくという流れになっています。
本日の講義内容
まずはPESOですね。ここはMARPSでも「つながる思考術」のPESOの回のところで、今日お話をする内容の6割ぐらいは徹底的に話しているので、その回をもうすでに聞いたよっていう方は、今日はもう1回学習ですね。
初めての方は、マーケティングコミュニケーションの施策を考えていく上でめちゃめちゃ重要なのが、このPESOを徹底的にきっちり正確に理解するというところになりますので、今日のメインディッシュはこの6番目のPESOを理解するといったところに置いてもらって構いません。
もうちょっと細かく、しっかりと施策の設計とかができるようになりたいぞという場合は、やはり7番目の「真実の瞬間」とか「クチコミには4つあるよ」という話、特に後で紹介するZMOT(Zero Moment of Truth)ですね、ここを理解すると、もう一段階解像度が上がります。そして最終的にこのファネルマップをどのように考えていくのか、みたいなところが最後に8つ目で今日は終了という風な回になります。
2. マーケティングコミュニケーションの役割と限界
売上の地図における位置づけ
こちらが先週徹底的に復習をした「売上の地図」です。今話をした通り、この売上というのは単なる結果ですから、この結果としての売上の出力を上げるためには、入力を上げていく必要があります。この入力の一番大きなものは、この「売り場」と「想起」です。いろんな変数が結局は全部矢印がつながってここに集約され、最終的にはこの売り場と想起が最大化することによって売上につながっていくという構造です。
この想起を上げるためにはプリファレンスを上げる必要があり、そのプリファレンスを上げるため、今日のメインのお題として、このプリファレンスの外側から囲んでいる入力として行うもの、広告、PR、オウンドメディア、ソーシャルメディアというメディア媒体を通して、いかにこのブランドに影響を与えていくかという回になっています。
マーケティングというのは、お客様に買っていただくことがゴールですよね。お客様に買っていただくために行う全事業活動がマーケティングです。いい製品を作ること、最適な値付けをすること、最寄り品であればできる限り全国津々浦々の多くのお店に商品を置いてもらうこと、お客さんが何を考えているのか、何に未充足なニーズを抱えているのかを把握するためのマーケティングリサーチも、全部マーケティングです。
「売上の地図」というのは、そのマーケティング全体の因果の構造を明らかにしたもので、この売上の地図というのは、ここにある通りマーケティング全体の因果の構造を俯瞰して見ることによって、自社の売上がもし足りていない場合、どこが足りていないのか、どこが接続されていないのかといったところのおよその当たりをつける、診断をするための一つのツールであると言えると思います。
マーケティングコミュニケーションでは解決できない課題
いろんな課題があります。例えば、製品のパフォーマンスがいまいち高くない、競合に負けているから売れないんだという場合は、製品そのもののパフォーマンスを上げない限りは売れません。製品のパフォーマンスがほとんど競合と変わらないのに値段がうちの方が高いから買ってもらえないというのは、価格の政策によるものです。
これらはマーケティングコミュニケーションで解決不能な課題です。広告とかPRとかオウンドメディアとかソーシャルメディアによる媒体を通じて製品やサービスの価値を伝えるという行為だけでは解決ができない課題です。
広告宣伝、PR、販売促進の担当者は、製品パフォーマンスや価格、チャネル政策の課題を解決することは仕事の領域には入りません。ですから、広告宣伝、PR、販促の担当者は、下の(売上の地図の)ところで見つかった課題のうち、マーケティングコミュニケーションで治療可能な病気を抜き出すということをまず絶対にやらなければいけません。つまり、何でもかんでも全ての課題をマーケティングコミュニケーションで解決することなんかできません、という意味です。
なので、今日このファネルマップの一番上のところ、広告とかPRとかオウンドメディアとかソーシャルメディアとかを活用しながら価値を伝えていくということを多くの皆さんはやっているのですけれども、その範疇の施策で解決ができるマーケティング上の課題、いまいち売上が上がらないという課題の全ては解決できませんよ、ということが大前提なんです。
多くの宣伝担当だったり、マーケティングコミュニケーションを担当している方々というのは、そのことを結構すっぽり忘れがちなんです。マーケティングコミュニケーションさえ頑張れば売上は上がるんだ、ないしは上からの圧力によって、マーケティングコミュニケーションの力だけで売上を上げなきゃいけないんだという風に考えてしまいがちですけども、そんなことはあろうはずがないというか、実現不能なわけです。
くどいですが、製品パフォーマンスが低くて買ってもらえない場合は、製品を改善しない限り売上は上がりません。製品のパフォーマンスが低いのに、広告の力だけでリピートの売上を上げることはできないですよね。
買う前に「買いたい」と思わせるコンセプト力と、買った後に「いいじゃん、もう1回買おう」「いまいち、もう買わない」というコンセプトとパフォーマンスの2つの掛け算によって、トライアルの売上とリピートの売上というのは形成されているわけで、広告とかPRの力で買う前に「買いたいな」と思わせる力を向上させることは当然実現可能です。
しかし、買った後にもう1回買いたいと思うかどうかというのは、広告やPRの力というより、ほとんどが製品やサービスのパフォーマンスによるわけです。あとは価格とか、買いやすさとか、そういった部分になりますので、マーケティングコミュニケーションだけでそのリピートの購入を促進することは現実的には不可能であるということです。
なので、今からこのファネルマップとかPESOを徹底的に復習していく回になりますけれども、その力というのは、ある種限定的なものだよ、といったところは絶対に忘れないようにしてください。そこが一番重要な注意点です。
3. ファネルマップの全体像と使い方
ファネルマップの構造と役割
こちらが今日復習をしていくマーケティングコミュニケーションのファネルマップです。いわゆるダブルファネルと言われているものに、いろんな施策は結局ここからここまでが対応範囲だよね、みたいなやつをまとめ始めてそろそろ10年ぐらい経つ気がするんですけど、やはり時代と共にどんどん施策が増えるので、この箱の数はもう多分一番最初にまとめた時から3、4倍ぐらいに増えているような印象があります。
世の中にいろんな施策があって頭がこんがらがっちゃったり、ぐちゃぐちゃになっちゃったりする方もいらっしゃるかもしれませんが、およそ代表的なマーケティングコミュニケーションの施策というのは、もうこのファネルマップのどこかに入っているという風に思っていただいていいと思います。まずはこのファネルマップの1個1個をきっちり正確に理解をするといったところができれば、十分なんじゃないかなと思います。
ファネルマップの超当たり前の復習をしておきますと、カスタマージャーニーマップというのはお客さん視点で考えていくのが原則としてあって、ファネルマップというのは大体売り手発想で作られるということが昔から言われています。売り手発想で作られているからダメだ、顧客視点で作り替えよう、というのがカスタマージャーニーマップになったと言われています。
しかし、ファネルマップはファネルマップで今でも有用で、結局カスタマージャーニーマップも上のところは「商品を知ってもらう」「興味を持ってもらう」「比較検討して買ってもらう」ということが書かれているんですよね。それって結局ファネルと同じというか、顧客の購買プロセスそのものがジャーニーマップの上にもありますので、考え方としては非常に近い、ほぼ同じだと僕は思っています。
大事なのは、
- 知らないお客さんに商品を知ってもらうにはどうしたらいいのか?
- 知ってはいるけど興味がない人にどうやったら興味を持ってもらえるのか?
- 知っててある一定の興味はあるけれど、オタクの商品と競合の商品の何がどう違うのかよく分かりません、という人にどうやったら理解を促進して購入の意向を上げていくか?
- 実際の比較検討になった時に有利に進めるには?
- 最終的に商品を買ってもらうために背中を押す、販売促進的な施策としてはどんなものがあるのか?
というように、左側からできる限り多くのお客さんに入ってきてもらって、いい歩留まりで右に移動していってもらうことを考えていくのが、このファネルマップの役割です。
施策は「薬」、課題は「病気」
大事なのが、この箱の横幅です。どこから始まってどこで終わっているのか。結局、1つの施策で全てのフルファネル、一番左の潜在顧客育成から一番右のロイヤルティの形成までをぶち抜いてできる施策というのは、この世には存在していないということです。
お薬と全く同じで、頭痛薬は頭痛にしか効かないし、胃腸薬は胃腸にしか効かないのと同じで、何かの施策というのは、どこかのマーケティングの課題をピンポイントで解決することに特化している「お薬」であるという考え方がとても大事なんです。
皆さんの商品も、まだ知らない人もいるし、知ってるけど興味を持っていないお客さんもいるし、理解ができていないお客さんもいる。このファネルマップ上にいろんなお客さんがバラバラといるわけです。
ただ、今の皆さんが持っている今期の予算で、今期の売上の目標を達成するにあたって、どこのお客さんが一番多く堰き止められちゃっている場所はどこなのか。要は「病気」をしっかりと見つけ出して、そこの課題をピンポイントで解決するためには、例えば理解が促進できていないお客さんがいっぱい滞留しちゃっているということであれば、認知向上施策や興味喚起施策じゃなくて、「理解促進施策」に最も時間とお金をかけなきゃいけないということですよね。
およそこのファネルマップで、今解決しなければいけない課題、お客さんがどこで止まっているのかを明らかにした上で、それが「診断」です。診察・診断して、じゃあそこの病気を治すために、その病気を一番治すことが得意な「お薬」を飲んで治そう、というのが施策を講じる、施策を選択するということです。
各施策の効能を理解する重要性
なので、この1個1個のお薬がどこに効くのか、逆に言うとどこには効かないのか、というところの解像度を高める必要があります。理想は、1回このファネルマップの箱を全部取って、扇型のファネルだけを書いて、テレビCMとか新聞広告とか記事タイアップとか、そういった項目があった時に、このファネルマップを見ないで、自分で正確に「この施策はここからここまで効くけど、ここには効かない」というのを再現できるかです。
それができる状態になっていないということは、どの施策がどこに効いてどこに効かないかということが、まだ正確に自分の腹に落ちていない、把握できていない状態なので、診断が合っていても処方で間違っちゃうリスクがまだまだあるということです。
今日はPESOを徹底的に復習するので、このファネルマップの中にある1個1個の施策は結構細かいんですけど、結局は4つに分けられます。それがPaid、Earned、Shared、Ownedの4つに分けられるので、まずはこの4つの大きな分類を理解すると、そこそこ大外しはしなくなるところまでを目指すという回になります。
4. マーケティング施策のよくある誤解
社内で起こる「不毛なやりとり」
『マーケティング「つながる思考術」』という本を書いたのは、強い問題意識があったからです。皆さんにも心当たりがあるような、社内での不毛なやりとりというのが世の中ですごく量産されていて、全然減る気配がないわけです。「全然バズんないじゃん」「バズったけど売上上がんないじゃん」とか、「フォロワーが増えないじゃないか」とか、「SNSやってるけど全然サイト集客に繋がんないじゃん」とか、「これ意味あんの?」とか言われちゃったり。
コンテンツマーケティングも同じです。BtoBも、買い回り品や専門品も、マーケティングの力でお客さんのニーズを喚起することはほぼ難しいわけです。住宅メーカーがすごくいい家を作れるぜとやっても、家を買う人の総数が増えるかというと、それは難しい。そろそろ家を建てたいな、という人がその広告に反応することはあるかもしれないけれど、新築住宅の着工数そのものが増えるわけではない。
これはBtoBも同じで、一社の努力によってお客さんのニーズを強制的に喚起することはほぼ不可能だと思っています。なので、我々にできるのは、お客様と良質な接点を持ち続け、お客さんのニーズがいよいよ顕在化した瞬間に、「あ、ちょっとトライバルさんに相談してみようかな」と想起してもらうことなんです。これがコンテンツマーケティングの一番重要なポイントです。
ということは、コンテンツマーケティングのKPIは、今まだニーズがそんなに顕在化していないお客さんと、どれだけ良質な接点を持つことができているのかというところが重要なわけで、「コンテンツマーケティングによって今期どれぐらいのお客さんを刈り取ったのか」みたいなところは、本来的にKPIとして設定してはいけないはずなんです。
コンテンツマーケティングのCPAが高いじゃないか、と言っているのは、ゴールキーパーを捕まえて「なんでお前今日の試合で1点も入れてないんだ?」と言っているのとほぼ同じツッコミなんです。これも結局、さっきのファネルマップの中の1個の薬、頭痛薬を捕まえて「なんでお前は胃腸に効かないんだ」と言っているのと同じなんですよ。
マーケティングの施策は、別に効能効果がどこにも書いてないから、みんなそれぞれ解釈がバラバラなんです。だから、この『つながる思考術』を書いて、1個1個の薬の効能効果をみんなが理解することによって、こういった不毛な議論をなくすことができるんじゃないか、といったところを目指しました。
動画マーケティングも同じです。流行っているから何でも動画にしようとしますが、動画はテキストや画像に比べると時間とお金がかかるわけですから、普通にやったらCPAは上がります。
でも、その動画を見て、今は買わなかったけど、リッチなコンテンツが脳に刻まれて、半年後に思い出して買ってくれるかもしれないですよね。なので、動画マーケティングは短期的なCPAだけじゃなくて、中長期的なブランドリフトの効果みたいなものを合わせて測定しないと、結局「なんで動画なんか作っちゃったの?」みたいな話になってしまう。
そして、僕がこの世で一番嫌いなフレーズが「で、それやったらなんぼ売れんの?」です。売上の地図なんです、因果の構造だから、自動販売機のボタンみたいに、この施策を投じたら売上がコトンと落ちてくるような単純な話じゃないんです、という話です。
「魔法の施策症候群」という罠
無理もないことで、この10年間で施策の数は2倍、3倍に増えています。アドテクノロジー等の進化によって、今までできなかったことができるようになったのは素晴らしいことですが、次から次に新しい薬が出てくるので、その薬の効能効果を理解しないまま、なんとなく「新しい新薬が出たから飲んでみよう」みたいなことが起こっ ちゃっ てるということです。
そして、「今までの施策は効き目が悪い。今度出たこの薬は本物だ。この薬さえ飲めば売上はバコッと上がるんだ」と、なぜか新しい薬に過剰な期待を寄せてしまいがちなんです。これを「魔法の施策症候群」と僕は言っていますが、そんなものはこの世に存在しないので、まず「この薬だけ飲めば全ての課題が解決するような魔法の薬なんて存在しないんだ」ということをちゃんと理解し、そこからブレなければ、余計な時間もお金も使わずに済みます。
最も重要なのは「診断」と「処方」
どの薬を飲むかどうかは、新しいかどうか、どこかの会社が成功したかどうかも関係なく、皆さんの病気に合った薬を最適なタイミングで飲むだけ、それだけの話です。なので、新しいとか、事例とか、派手なものに一切振り回されない方がよろしい。
医療ミスの90%は、だいたい診断ミスか処方ミス、もしくはその両方から発生しています。世の中のマーケティング施策の7、8割は、だいたい診断か処方か、両方が間違っている、と僕は感じます。なので、まずしっかりと診察・診断して、自分の病気を特定する。それは競合とは違う病気のはずです。違う病気なんだから、競合と同じ薬を飲んでたってしょうがないわけです。
口を酸っぱくして言いたいのは、皆さんはマーケティングコミュニケーションとか施策とかになると、すぐ何かやろうとしちゃう、実行しようとしちゃうんですけど、『イシューからはじめよ』という大ベストセラーがある通り、自分は一体どこが悪いんだということを、ちゃんと診察・診断する。診察・診断が正しければ、もう7割方勝ちです。
それぐらい、診察・診断を間違うし、診察・診断をすっ飛ばして薬ばっかり飲んでいる。病気が特定できていないのに、当てずっぽうで薬を飲んで効くなんてことはまずあり得ないですよ。
なので、徹底的にちゃんと診察・診断しましょう。その診察・診断をするための問診票として、今までMARPSで話しているような「売上の地図」も「ファネルマップ」も「真実の瞬間」のフレームも、いろんなツールがあります。ああいったツールは診察をするための問診票みたいなもんです。病気を特定するということです。
ここさえできれば、あとは今日お話をする薬の理解です。この薬は何に効くけど、何には効かないのか。薬剤師として、しっかりと施策の理解、薬の理解ができていれば、診断が合っていれば、この病気を一番治すのが得意な薬を飲めば治る確率がとても高い、ということです。
効果検証で陥りがちな5つのケース
全ての施策は必ず売上に向かっているはずです。やっている施策によって変数が変わり、KPIが上がって、結果として売上が上がる、ということをやろうとするわけですけど、世の中の7、8割方は、大体このケース1からケース4の状況になっちゃっています。
- ケース1: 診断をしないで、手段が目的化する。「流行ってるから」とか「面白いことやりたい」とかで施策をやって、終わった後に「これって結局何のためにやったんだっけ?」となるパターン。
- ケース2: 診断そのものを間違う。診断が間違っているので処方も間違う。成果が得られないと、診断が違ったとは言われず、「この薬、全然効かねえじゃん」と薬のせいにされるパターン。
- ケース3: 診断は合っているが、処方を間違う。「認知が低いから認知を向上させよう」までは合っているのに、「じゃあTikTokでバズるドラマ作ろうぜ」みたいなことをやってしまう。これも薬のせいにされるが、処方が間違っているパターン。
- ケース4: 診断も処方も合っているが、成果を「売上」で見てしまう。「テレビCMで認知は上がったけど、売上上がってないじゃん」となって、CMはオワコンだ、みたいな解釈をしてしまう惜しいパターン。
- ケース5(理想): 診断も処方も合っていて、成果の指標も売上ではなく、1つ手前の変数のKPIでしっかり測っている。目標が100で結果が85だった時に、「あと15を埋めるために、次回は何をどう改善すべきか」という議論をしていくのが一番健全な状態。
マーケティング施策は、診断と処方が合っていても、なお成功する確率は1割、高くても3割がいいところです。なので、しっかりこのケース5の状態で振り返ることができるかどうかがとても大事なポイントです。
5. メディアの4分類「PESO」の徹底解説
なぜPESOを理解する必要があるのか
1個1個の薬に対する理解が皆さんものすごく曖昧なまま、その薬を飲んだり飲み続けたりしていることが、「こんなはずじゃなかった」のすごく大きな要因になっています。今日は、まずざっくりと4分類のPESOでできることとできないことをきっちりと理解することがゴールになります。
「売上の地図」で言う通り、想起を上げたい。そのためにはプリファレンスを上げる必要がある。プリファレンスは「価格」「ブランドエクイティ」「製品パフォーマンス」から成り立ちます。
価格と製品パフォーマンスはマーケティングコミュニケーションでは影響を与えられないので、ブランドエクイティを上げるために、メディアからのインプットによってブランド価値を向上させたいわけです。
そのメディアは大きく分けるとこの4つ、PESOです。ファネルマップの細かい施策も、この4つの箱にそれぞれ全部整理できますから、まずはこの4つの違いをきっちり理解することです。
メディアを介したコミュニケーションの基本
マーケティングコミュニケーションというのは、皆さんの製品やサービスの価値をお客様に伝えるという仕事です。価値を伝えるためには、必ずこの真ん中に媒体というものが介在しているわけです。1個1個の媒体の特性というものを理解していないと、使い方を間違っちゃうってことです。
そして、伝えているということと、伝わっているというところが合致していないことがほとんどです。昔に比べて格段に伝わりづらくなっているので、「伝えた」じゃなくて「ちゃんと伝わったか」を徹底的に考えて実行し、検証していかないといけません。
メディアには、企業側から情報を届けるプッシュ系のものと、オウンドメディアのようにユーザー側からやってくるプル系のものがあります。また、メディアやシーン、デバイスごとに接触する時の「態度」が違うことも理解しておく必要があります。テレビCMとYouTubeの強制視聴広告では、同じ15秒でもユーザーの受ける体験が全く違うわけです。
さらに、どれだけ多くの人に届けられるかという「リーチの広さ」、つまり線の太さも重要です。率だけでなく、人数でちゃんと検証するという考え方もとても重要になります。
1. Paid Media(ペイドメディア:広告)
マーケティングコミュニケーションの中で最も多くのお金が使われているのが広告、ペイドメディアです。マス広告だろうが、デジタル広告だろうが、交通広告だろうが、広告のフォーマットでコミュニケーションがなされているものが相当な分量を占めています。ファネルマップで言うと、このピンク色のところが広告です。
インフルエンサーマーケティングも、最近行われているものの大多数は報酬を支払ってPRタグをつけて投稿してもらう施策なので、結局は広告です。
広告のメリットは何かと言ったら、「コントローラブルである」こと、これに尽きます。出したいメディアに、出したい時期に、出したいクリエイティブで、出したいだけ出すことができる。これが広告の一番のメリットです。
一方で、これだけ消費者が賢くなって疑い深くなると、広告で「すごい」「うまい」と言っても、「まあ広告なんだから、そりゃいいことばっかり言うよね」と信じてもらえなくなってきています。認知を獲得するには、相変わらず広告が最も効果が高く、効率もいいです。しかし、認知したら買ってもらえるかと言ったら、全然別の話です。
結論として、ペイドメディアは他の3つと比べると圧倒的に認知獲得力が強いです。極論を言ってしまうと、認知というのはお金で買うものなんです。お金をかけずに認知を向上しようとするから、だいたい間違う。認知を上げたいなら、広告で認知を買いなさい、という話です。
お金で買えないものがあります。それが「好意」だったり「信頼」だったり「興味を喚起する」ことだったり。広告だけでは、これらを上げることがすごく難しい。入り口の認知を獲得するのは広告が一番得意です。
2. Earned Media(アーンドメディア:PR・パブリシティ)
アーンドメディアはPR、その中でも特にパブリシティと考えてください。新商品や新サービスをできる限りニュースとして取り上げてもらうようにする活動です。
PRはなぜ効果が高いかというと、企業がコントロールできないからです。広告は企業が全てをコントロールできるから、あまり信じてもらえない。でも、PRの情報は第3者としてのメディアを介して発信されるので、みんな興味を持つし、信頼するわけです。だから、PRの一番の効果は、認知を向上することではなく、広告の弱みである信頼性(クレディビリティ)を上げることができる、これが一番の強みです。
広告にできない興味喚起力、好意・信頼の向上、購入意向の向上があります。しかし、弱点は「アンコントローラブルである」こと。どのメディアに、いつ、どんな文脈で、どのような表現で出るのか、全て決められません。
なので、Paidが認知獲得メディアであるのに対し、Earnedは興味喚起・好意・信頼度を獲得するメディアである、という整理ができます。
3. Owned Media(オウンドメディア)
オウンドメディアは、多くの場合、検索経由でやってきてくれます。つまり、お客さん側が何かを想起し、検索してやってくる場所なので、基本的にすでに皆さんのことを知っている人しか来ません。特に指名検索の場合は、すでにある一定の興味があるから、わざわざ検索してオウンドメディアにやってきているわけです。
ということは、オウンドメディアの役割は何か。認知されていて、興味も喚起されている。もっと知りたいと思っている人たちに、ちゃんとその情報をきっちり伝えてあげることで理解を促進してもらい、購入の意向を上げることです。
だから、オウンドメディアのKPIでよく取られるPVやUU、滞在時間は、ただの手段であって目的ではありません。オウンドメディアのKGI(最重要目標達成指標)は、知りたかったことが理解できたか、それによって応募や問い合わせ、購入の意向が上がったかどうか、であるはずです。
4. Shared Media(シェアドメディア:ソーシャルメディア)
ソーシャルメディアは、公式アカウント、タイムラインを流れるUGC(いわゆるバズ)、そしてレビューサイトなど、多方面にわたるため、一言でまとめるのは非常に難しいです。
あえて一括りで説明するなら、タイムラインで誰かが投稿しているのを見て「え、流行ってんの?」と興味を持つ効果、共感する効果、自分もやってみたいと思う意向を上げる効果などがあります。レビューを見て「これなら間違いないな、よし買おう」と購入意向の最後のダメ押しをすることもあります。
まとめると、シェアドメディアは興味・共感・意向獲得メディアと言えると思います。
メディアの組み合わせと影響力の変化
マーケティングコミュニケーションの施策は、結局この4つに集約され、それぞれ役割が全く違います。なので、何か1つをやって売上を上げようとするのではなく、いかに組み合わせるかが大事です。強みと弱みが全然違うので。
近年、影響力は広告(Paid)中心から、PR(Earned)やソーシャル(Shared)へと移行してきています。なぜ消費者は右側(Earned/Shared)で影響を受けるようになったかというと、企業がコントロールできないということを分かっているからです。企業がコントロールできるものは、額面通りには信じない、というわけです。
昔はマーケターがお金でコントローラブルな施策で全てを設計できましたが、今は企業が必ずしもコントロールできない領域が拡大しているので、そこを理解した上でどううまく企画設計できるかが大事になってきています。
6. 4つの「真実の瞬間」とクチコミの役割
消費者が評価を下す4つのタイミング
消費者は皆さんのことを4回評価しています。
- ZMOT (Zero Moment of Truth): 店頭に行く「前」に、ネットで検索したりクチコミを見たりして、買うものをあらかた決めてしまう瞬間。
- FMOT (First Moment of Truth): 店頭で商品棚を前にして、買うか買わないかを決める瞬間。
- SMOT (Second Moment of Truth): 購入した商品を実際に使ってみて、そのパフォーマンスを評価する瞬間。
- TMOT (Third Moment of Truth): 購入後も継続的にブランドを体験し、評価が上書きされていく瞬間(線の評価)。
この中で、今最も重要なのがZMOTです。店頭に行く前に勝負の7〜8割が決まっているなら、ZMOTがめちゃめちゃ大事じゃないですか。
そして、このZMOTに影響を与えるのが広告、PR、そしてクチコミ(シェアド)です。顧客が良い体験をすると、それがクチコミとなって次の新規顧客のZMOTを形成するという循環が生まれています。
クチコミを2種類に分けて考える
このZMOTに影響を与えるクチコミには大きく2種類あります。
- タイムライン型UGC(フロー型): TwitterやInstagramなどで流れていくクチコミ。人によって見ているものが違い、どんどん流れていきますが、話題が広がれば多くの人に届き、「みんなが言ってるから気になる」という、認知や興味喚起に影響を与えます。
- 検索型UGC(ストック型): レビューサイトなど、能動的に検索して見に行くクチコミ。ストックされていき、誰もが同じ情報を見ることができます。「失敗したくない」という心理で読み込まれ、理解促進や比較検討に影響を与えます。
ファネルマップ上でも、タイムライン型UGCは認知・興味喚起の左側に、レビュー(検索)型UGCは購入直前の右側に位置づけられます。
7. 商材特性によるアプローチの違い
7. 商材特性によるアプローチの違い
一般消費財のファネルマップ
スーパーやコンビニなどで買う一般消費財は、購入リスクが低いため、いちいち検索しません。大事なのは、店頭に行く「前」に、「マヨネーズならキューピー」のように無意識に思い出してもらう状態(想起)をZMOTで作り上げることです。
施策はシンプルなので、ファネルマップにおける理解促進や比較検討のフェーズはほぼ不要です。つまり、このグレーアウトしている部分の施策は考えなくていいということです。無駄なことをやりすぎず、やるべきことに資源を集中させることが重要です。
耐久消費財・専門品のファネルマップ
車、住宅、BtoBなどの耐久消費財や専門品は、購入までの期間が長く、リスクも高いため、徹底的に検索されます。
まず、ニーズが顕在化した時に「車を買い替えるならA社かB社かC社」という想起集合に入っていることが勝負の半分を決めます。その後、検索された時に、質の良いレビューが十分な量あるかどうかが、売上にダイレクトに影響します。BtoBマーケティングもこちらに含まれ、ニーズが顕在化する前の潜在顧客の時期に、いかにブランドをすり込んでおけるかが重要です。
8. まとめ:成功するマーケティング施策の要点
診断の重要性と「やらないこと」を決める勇気
今日の講義のまとめです。
- 施策がいまいち効かない時は、薬のせいではなく、診断が間違っていることをまず疑ってください。
- 自社の商材特性に合わせてファネルマップをカスタマイズし、「何をやらないか」を決めることが重要です。 自社の商品カテゴリーでは意味のない施策、やらなくていい施策を部内で決めてしまうことをお勧めします。マーケターの「新しいことをやりたい」「面白いことをやりたい」というエゴは、時に邪魔になります。
提出義務のない宿題
提出義務のない宿題です。各施策で「できること」に皆さんは注目しがちなので、逆に**「この施策でできないことは何か?」**を考えてみてください。これが分かっていれば、薬の飲み間違いはほぼなくなるはずです。効能効果ではなく、効かないところをちゃんと答えられるようにしてください。
来週はお休みで、再来週からは新たに「デジタルマーケティング連続講座」が始まりますので、ぜひご参加ください。
ということで、今日の講義はこれにて終了です。また再来週お会いいたしましょう。お疲れ様でした。