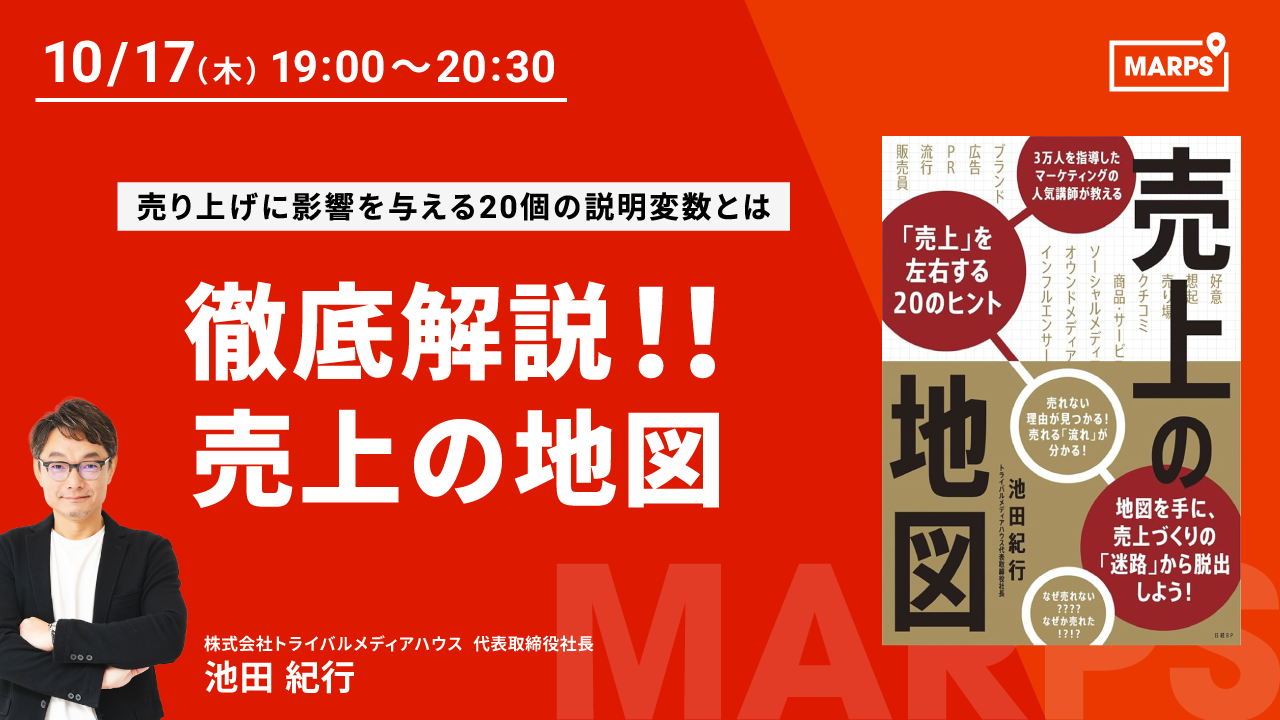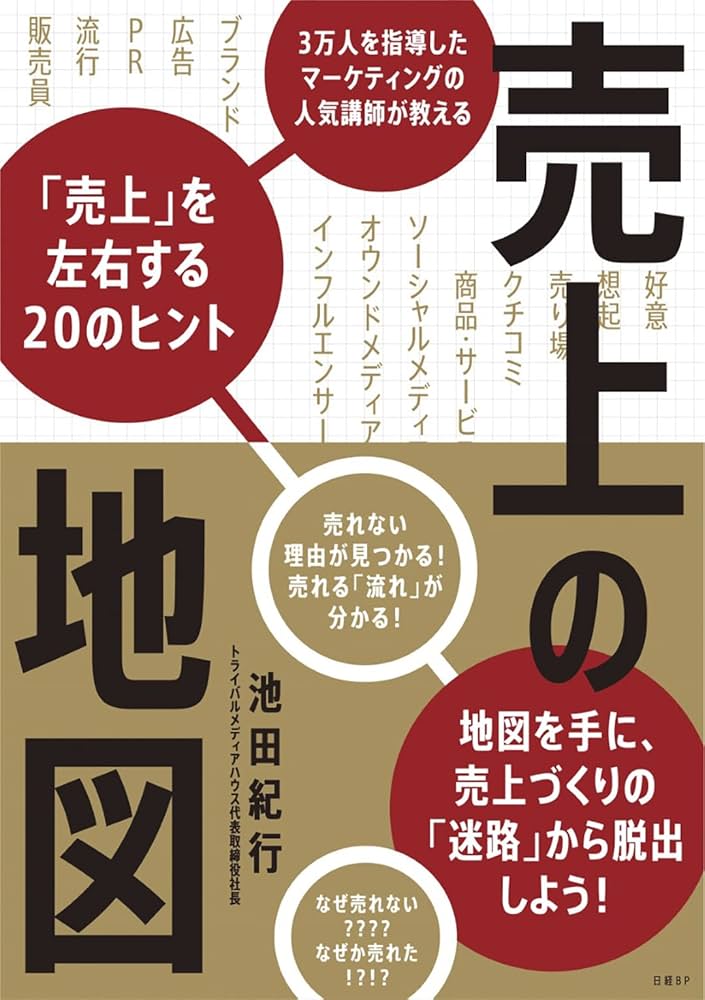はじめに:『売上の地図』を「線」で理解する総復習
皆さん、こんばんは。今週も始まりました、木曜日のMARPSでございます。有斐閣アルマのマーケティング戦略の全14回講座が終わって、3週間ぶりですね。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。
今週と来週、2回連続で『売上の地図』と「マーケティングコミュニケーションのファネルマップ」を徹底的に総復習する回をやります。今日が『売上の地図』で、来週が「コミュニケーションのファネルマップ」なのですが、これらは切っても切り離せないので、申し訳ないですが2回連続で聞いていただかないと繋がらない構成になっています。なので今日は全体のプログラムの半分までやって、続きは来週ということになります。
私は『売上の地図』を書いて、次に『業界別マーケティングの地図』を書いて、同時に『マーケティングのつながる思考術』という3部作を2022年から23年にかけて書いてきたわけです。これらは一個一個別に書いていますが、全部繋がっています。売上にはトライアル売上とリピート売上があります。売上を上げるためには「売場」と「想起」が大事で、「想起」のためにはプレファレンスを上げる必要があります。
そして、プレファレンスを上げるためにマーケティングコミュニケーションの施策が存在している。全部一個一個繋がっていて、その繋げて線で理解をするために一個一個の点を理解していないと線として繋がらないので、点を学ぶという構成になっています。
今日も『売上の地図』の解説をしますが、本では説明変数を一個一個、20個を断片的に「点」として解説しているので、今週と来週でやりたいのは、皆さんが点として学んできた色々な概念や、一部の方は線として繋がり始めているであろう抽象的な概念やフレームみたいなものが、いかに結局一個のことを言っているのかを、体系的、つまり線として理解する機会にしてもらえたらなと思っています。
なので、今日お話しするスライドは、MARPSのヘビーユーザーの方からすると、新しいスライドは多分ありません。今まで、私も1年で40回ぐらいMARPSで講義をやりましたが、どこかの講義で話している内容です。ただ、もう一度『売上の地図』や「ファネルマップ」、あるいは業界別のカテゴリーの関与度別に商材と向き合う時に、線としてちゃんと繋げるということは今までやってこなかったので、スライドとしては新しいものはないと思いますが、もう一回総復習をしてもらうという感じで聞いてもらえたらなと思います。
参加者の状況確認
最初にウォーミングアップをしましょうか。チャットを開いていただいて、いつも火曜日のゲストの時にやっているのですが、せっかくなので聞かせてください。宛先を全員にしてもらって、『売上の地図』を「読んでいるぜ」が1番、「読んでいる途中です」が2番、「今日の話が面白かったら読もうかな」という方が3番だとすると、皆さんどんな感じでしょうか。教えてください。
ありがとうございます。1番の方もまあまあいらっしゃり、「使っている」という方もいますね。2番も3番もちょこちょこいらっしゃる。ということは、今日初めて知りました、という方も3分の1ぐらいいそうですね。ですが、半分ぐらいの方は復習みたいな感じでしょうか。何回聞いてもいい話だな、となるように心がけてお話をしますが、初めての方にも分かりやすくお話をするようにしますね。
なぜ『売上の地図』が必要なのか? ―売上の「因果構造」を解き明かす
さて、ではいきましょう。ページ数がまあまああるので、ざっといきますよ。
売上は「結果」であり、インプットに目を向けるべき
まず、なぜこの本を書いたのかというところからもう一度復習しておくと、この「因果関係」「因果構造」というものを明らかにしたかったからです。逆に言うと、マーケティングの現場で日々お仕事をされている方々が、意外なほどにこの因果構造で売上を見ていないというところに、すごく強い問題意識を持っていました。
この「因果」がキーワードになるのですが、因果関係を示すものに「因果応報」があります。日本昔話などは大体この因果応報で、いいことをしているおじいさん・おばあさんは大体幸せになるし、それを隣の家から見て羨ましがっている意地悪じいさん・ばあさんがろくでもないことをすると、最後は大体不幸な結末が待っている、というものですね。これが因果関係の因果応報です。「風が吹けば桶屋が儲かる」も全部因果関係ですよね。Aの入力によってBが出力され、さらにそのBが入力になって次のCが出力される、というものです。
世の中のほとんどの事象、つまり出力されているアウトプットには、必ず何かしらのインプットがあります。結果には必ず原因があるということです。だから、「売上が上がった」「売上が下がった」というアウトプットは、必ず何かしらのインプットがあるからその結果になっている、ということです。
これは、日経クロストレンドの「マーケター実態調査」からの引用ですが、「KPIとして何を重視していますか」という調査です。ここにある通り、売上、新規顧客の獲得数、顧客数、利益、リード、コンバージョンレート、ライフタイムバリューなど色々あります。しかし、これらは結局全部「結果」、単なる出力された結果なのです。
いつも言っていますが、「売上が上がった」「下がった」、「ライフタイムバリューが想定通りに上がらない、下がってきた」、「顧客数が増えない、減ってきた」というのは、全部結果です。なので、それを直接見ていても何もなりません。
「売上を上げたい」なら、「じゃあどうするの?」、それがインプットですよね。「ライフタイムバリューが想定通りに上がらない」なら、「じゃあどうするの?」となるわけです。皆さんの会社の会議、特に営業会議などはその最たるものですが、ずっとこのアウトプットを見て、みんなで一喜一憂しながら「どうしよう、どうしよう」と言っていることがかなり多くないですか。
売上が上がらない原因は一つではない
結果として、売上が絶好調で上振れして大変だ、というところは少なく、大体は立てている目標に対して実績がついてこないことの方が多いわけです。つまり、一番右側のKGIが100%欲しいのに、目標に対して40%しかいっていない、0.4だということです。
では、何が悪さをして最終的な出力、つまり売上が上がらないのかと考えた時に、多くの企業が上の「パターンA」で考えがちです。「どこがボトルネックなんだ」「どこで水が止まっているんだ」と明らかにしたがる。そうすると、「KPI①が0.4だから、他は良いのに出力が0.4になっているんじゃないか」と解釈しがちです。
しかし、我々がコンサルで入ってジャーニーや『売上の地図』を考察していくと、ほとんど、ほぼ100%が「パターンB」です。色々なところがちょっとずつ悪い。色々なところがちょっとずつ悪くて、掛け算すると最終的に出力が0.4になっているということです。そんなに単純ではなく、悪さをしているのは1箇所じゃないということです。
では、このKPI①②③④を明らかにして一個一個解決していけば良いじゃないか、という話になりますが、なかなかそこまで簡単なものではありません。これらは因果関係で繋がっているからです。並列で並んでいると分かりやすいですが、現実のマーケティングはこんなに並列に物事が並んでいません。私がいつも言っている、ダイエットの例で言うと、体重が売上だとします。売上は上げたい、体重は下げたいわけですよね。
ダイエットはほとんどの人がやったことがありますが、うまくいかなかったという結果になることが多いですよね。売上ととても近いです。上げたいけれども、思うように上がらない。では、なぜ体重を下げられないのかというと、体重を減らす方法が分からない人はいません。食べる量を減らすか、消費カロリーを増やすか、両方やるかの3つしかないわけです。
では、なぜこんなに簡単なことができないのかというと、結局、その下にある変数が構造的な問題で悪さをしているからです。結果として摂取カロリーは減らないし、消費カロリーは増えない。そして最終的な出力としての体重が減らない、ということです。
売上も結局同じで、「売上!」と言っていても上がるわけはありません。売上の一個手前にある重要な変数は何か、そしてその変数も実は接続された結果なのです。では、なぜその変数が上がらないのかというと、さらにその下に色々な変数が隠れている、ということです。そして、ここにある通り、全ては構造的に繋がっているからです。一個一個が単独で、直列で何かに影響を与えているわけではありません。
例えば、仕事が超忙しいと、昼飯を食いっぱぐれて夜遅い時間にドカ食いしたり、飲み会が多くてお酒を大量に飲みながらこってりしたものを食べたりする。夜遅いので家に帰ってすぐ寝るわけですが、ストレスもあるし、食べたばかりで胃がパンパンなので眠りが浅い。朝起きてもストレスは解消されず、睡眠の質が悪くて疲れが取れていない。それがまたぐるぐる回るわけです。結果的に、摂取カロリーがいつまでも思うように減らない、という感じになります。
こういう時は、仕事、ストレス、睡眠、飲み会、お酒の量といったものが構造的に繋がっているので、そこを解消しない限り、結果的に摂取カロリーは減らない、という話です。
なので、全ての出力には入力がある。アウトプットばかり見ていてもしょうがないので、売上という単なる結果を増やすために、インプットにとにかく目を向けましょう、という話。もう一つは、このインプットは、一個インプットしたらすぐにアウトプットに直結するのではなく、構造的に効いてアウトプットに繋がっているということです。
どの施策が効いたのか?ブラックボックス化するマーケティング
皆さんの会社の規模が大きく、使える予算が多いほど、大体同時に色々な施策を並行して行っていますよね。売上を上げるために色々な施策を同時にやるわけです。そうすると左側から同時に5つのインプットが走るわけですが、真ん中がブラックボックスになっているので、アウトプットとしての売上は月で締めれば分かります。
しかし、どの施策のインプットが効いてこのアウトプットが出ているのかが分からないわけです。分からないけれど、「多分このインプットが効いてこのアウトプットになっているんじゃないの」と考えるのですが、大体分析すると、一個一個のものはそれなりに全部効いています。何かが効いていなくて何かが効いているというよりは、色々なものが構造的に繋がって最終的なアウトプットになっているのです。
なので、どの施策が良いか悪いかを考えてもあまり意味がありません。どの施策がどんな因果の構造をなして最終的に売上に繋がっているのかを明らかにしていく必要があります。因果の構造を明らかにすること自体は手段であって目的ではないので、何のために明らかにするのかというと、限られた資源で限られたインプットをできる限りアウトプットに繋げていくためにどうしたら良いのかを考えるためです。そのためには、真ん中がブラックボックスでは駄目なのです。
自動販売機ではなく「電子回路」で考える
世の中では「売れた」「売れなかった」という話がそこら中でされていますが、「売れた」となると、大体「私がやったこの施策が良かったんだ」という話になりがちです。CMが良かった、タレントが良かった、商品が良かった、営業が頑張ったからだ、口コミやインフルエンサーの投稿でバズったからだ、と色々ありますが、そんなに単純な話ではありません。
売上というのは、自動販売機のボタンを押すようなものではなく、極めて電子回路のように、色々なものを通過して最終的に豆電球が光っている、つまり売上が上がっている、ということなのです。期待している売上、豆電球の光量が弱い、つまり売上が想定よりも上がらない時に、どの施策が効いているのかいないのかという自動販売機的な思考で考えるのではなく、電子回路が構造的に繋がって電気が光っているわけですから、「どこが断線しているんだろう」「どこの抵抗が悪くて電力が落ちているんだろう」という思考で考えていくことが大切です。
自動販売機のボタンを想像するのではなく、イコライザーのミキサーをチューニングしていくような考え方の方がしっくりきます。一個一個のイコライザーが構造をなしている変数なので、どこをどういう風に調整すると、限られた資源を有効活用しながら最終的な売上に影響を与えられるのか、ということを考えていく必要があります。
社内で共通言語を持つには
事前に、「社内で『売上の地図』のような考え方を共有できず孤独だ」「仲間をどう増やせばいいか」という質問ももらっていました。私が思う一番良い方法は、皆さんが担当している商品の売上に影響を与えている変数を、みんなで出し合うブレストをすることです。
例えば、デジタルマーケティングの話は、リスティング広告やバナー広告、リタゲ広告といった、極めて狭い話に終始しがちです。しかし、町にあるパン屋さんの売上に影響を与えている要因だけでもこれだけあります。パン屋さんでこれだけあるのですから、大きな商品やブランドになったらもっと変数はあるはずです。「なんで売上が上がらないんだろう」と思考停止している状態から、「うちの商品の売上に影響を与えている変数をみんなで出してみようよ」とワイワイ出すのです。
パン屋さんの例で見てみると、左側はマーケティングコミュニケーションとは関係ありません。味、品揃え、在庫切れ、値段、立地、駐車場の有無、店内の清潔さ、店員の対応などです。これらはコミュニケーションとは関係ありませんが、明らかに売上に影響を与えています。右側のチラシやLINEなどはマーケティングコミュニケーション領域です。それだけでなく、右下には、近くに大きなスーパーができたとか、美味しいパン屋さんができたとか、天候や気温といった外的環境の要因もあります。
結局、『売上の地図』というと小難しく感じますが、これを構造化しているだけなのです。抽象化して固めて、構造的に繋げて考えやすくしているだけです。図から入ってしまうと、「想起はどうなっているんだろう」「広告は?」「プレファレンスは?」といった抽象的な話になり、いつまでたってもよく分からない、となりがちです。
最初は具体でいいです。具体をとにかくたくさん出して、似たものを塊にして、最終的に矢印で繋げてみる。そうすると、変数が出てきて構造化ができていきます。そうすると社内でも、「売上が思うように上がらないのは、広告のやり方に問題があると思っていたけど、意外とそれだけじゃなくて、こっちもあっちも問題だよね」といったものが見えてきて、『売上の地図』的な会話ができ始めるのではないでしょうか。
広告効果とマーケティング効果を分ける「ベクトル図」
ソロモン・ダトカ氏の「ベクトル図」が全ての答えです。彼は、広告効果測定とマーケティング効果測定を明確に分けなさい、ごちゃ混ぜになっている、と言っています。つまり、「テレビCMに3億円、5億円を投じたけど売上が思うように上がらない。今回の広告は失敗だったんじゃないか」という話になりがちですが、広告だけで物は売れません。
広告の効果測定は、広告によって達成可能な指標でしか測ってはいけません。「広告を見て商品を知り、興味を持って欲しくなって買いに行ったけど、店頭に並んでいなくて買えませんでした」となったら、売上が上がらなかったのは広告のせいではありません。店頭に商品が並んでいなかった流通の施策がうまくいっていなかった、ということです。あるいは、広告は良かったけれど、店頭で見たら思った以上に値段が高くて買えなかった、競合の方が安かった、といった要因もあるわけです。
このベクトル図の細い矢印は、みんな右上、つまり売上を上げる方向に引っ張っていますが、売上という太い実線は、綱引きのようなもので、左下と右上で引っ張り合って上がったり下がったりしています。しかし、この売上を直接引っ張る紐は存在しません。これは出力だからです。細い縄が入力です。この入力の矢印を全部引っ張った結果として、右上に太い「売上」という結果が出てくるのです。
なので、広告効果測定は、広告で達成可能なもの、例えば認知度が何%から何%に上がったのか、というもので測るべきです。行為がどれだけ上がったのかを測ってもいいかもしれません。しかし、認知や行為が上がったのに売上が上がっていない場合、それを広告だけのせいにするのは、甚だ話がおかしいです。こういった複数の要因があって、それら全てがどれだけ売上に繋がったのかを分析するのが、マーケティング効果測定です。
もう一つの難しさは、全ての市場には必ず競合がいるので、自社の努力だけで売上は上げられないということです。最高の施策ができたのに、思ったほど売上が上がらなかった。なぜかというと、左下に競合がさらに強い力で縄を引いたからです。
高度に成熟化した市場では、昔のようにマーケット全体が広がっていたプラスサム市場とは違い、多くの市場がゼロサムゲームになっています。パイの大きさが変わらない、あるいは縮小しているということは、競合が上がれば自社が取られ、自社が取っている時はどこかの競合から取っている、ということです。
市場が拡大していないマーケットでの競争とは、自社の売上が1億円上がったということは、必ずどこかの競合の売上は1億円下がっているはずなのです。逆も然りです。なので、右上に引っ張っていくことと、競合にどれだけ引っ張られているのかを総合的に測っていくのが、トータルとしてのマーケティングの検証になってきます。
コミュニケーションだけでは売れない「CPバランス理論」
マーケティングコミュニケーションの領域の仕事をしている方が多いと思いますが、コミュニケーションだけで物は売れません、という話をいつもこの「CPバランス理論」でしています。Cはコンセプト、Pはパフォーマンスです。売上はコンセプトとパフォーマンスの掛け算によって作られるという考え方です。コンセプトは「買う前に買いたいと思わせる力」。これがトライアルの売上を決めます。パフォーマンスは「買った後にすごく良い商品だな、また買おう」と思わせる力。これがリピート購入に影響を与えます。
売上はトライアルとリピートの2つしかありません。右上(象限4)が一番理想で、トライアルが伸び、その多くがリピートしてくれると売上は上がっていきます。しかし、なかなかそうはなりません。ほとんどの商品は左下(象限1)です。コンセプト力が弱くトライアルが進まず、一部のトライアル客もパフォーマンス評価が低くリピートしないため、売上が上がりません。
多くの予算を持つ大企業の多くの新商品は、象限2です。クロスメディアキャンペーンで強制的にトライアル購入意向を高め、店頭を支配することで一定のトライアル売上を獲得できます。初動で売上は伸びますが、買った人が「言うほどでもないな」といつもの商品に戻ってしまうとリピートにならず、売上は下がってしまいます。
昔は象限3もありました。派手なプロモーションはしないけれど、買った人が「すごく良い商品だ」とリピートし、口コミでじわじわ売上が上がっていくパターンです。しかし今は、POSレジの導入により、初動で売れない商品は棚から外されてしまうため、じわじわ売れる時間的チャンスがありません。
ここで言いたいのは、売上が上がらない時は、トライアルが上がっていないのか、リピートが上がっていないのか、最低限2つに分けなければいけないということです。そして、リピートに繋がっていない時は、明らかに商品のパフォーマンス評価が低いということです。
「美味しい」と思って買ったら美味しくなかった、というような商品に次もリピートするわけがありません。そのリピート売上が上がらない要因は、広告やPRといったコミュニケーションの課題でしょうか。そんなことはないはずです。商品サービスそのものの力が弱いのです。これも売上の因果構造のど真ん中です。売上が上がらない時に、広告がどうとかPRがどうとかいうのは、本当に一部の話しかしていません。マーケティングとは、パン屋さんの話のように、もう全部なのです。
マーケティングミックスモデリング(MMM)の限界
各社が行っているマーケティング効果測定と言われるもののほとんどは、マーケティング「コミュニケーション」の効果測定の域を出ていません。「この広告でいくら売上が上がったのか」といったことをやっていますが、難しいです。出そうと思えば出せますが、本当かという疑問は残ります。なぜなら、全てはベクトル図であり、構造的に繋がって売上が上がったり下がったりしているからです。「この期間に出稿したこのテレビCMだけで売上はいくら上がったのか」なんていうのは、なかなか怪しい結果しか出ないと思っています。
最近、マーケティングミックスモデリング(MMM)が出てきて、重回帰分析によってどの施策が効いているのかを測れるようになってきています。しかし、入力している情報は、大体マーケティングコミュニケーションのデータだけです。商品やサービスそのものに対するパフォーマンスのスコアや、競合の強さ、天候、気温、ストアのカバレッジといったデータはほとんど入っていません。それらを入れるには莫大な時間と金がかかるからです。
そうすると、MMMをやっていると言っても、それはあくまで広告やPR、販売促進を足してどういう影響があったのかを測っているだけで、マーケティング全体のミックスモデリングにはなっていない、と私は理解しています。
本来は右側のアプローチでやっていかないと、正しい結果は見えてきません。売上は結果として見えているので、それが一体どの説明変数、例えばストアのカバレッジや商品のパフォーマンス、広告の出稿量といった変数を全部入れて分析しない限りは分かりません。ただ、そんなことを言ってもしょうがないので、最低限、因果構造を理解するために、地図として構造的に示してみんなで会話をスタートできる状態になれば、少なくとも左側よりは良くなるよね、というのが『売上の地図』を書こうと思ったきっかけでした。
地図を使いこなすための「俯瞰視点」
『売上の地図』を使いこなせるようになると、売上を俯瞰して見ることができるようになります。今は銀座の道のような景色で売上を見ようとしていますが、構造として繋がっているということは、上空から全体を俯瞰して見ないと、何と何が繋がってこの結果になっているのかが見えてきません。
『売上の地図』が読めるようになるということは、Googleマップのようにズームイン・ズームアウトができる視点を手に入れるということです。インとアウトを自由に行き来できるかどうかが、地図が読めるかどうかなのです。
原則1:マーケティングのやり方は商品カテゴリーによって全く異なる
この地図は、まずは俯瞰してどんな構造で売上が作られているのかをざっくり見えるようにすることが目的です。具体的な施策の話は次回のファネルマップの話になります。
『売上の地図』のカスタマイズが不可欠な理由
次に「業界別マーケティングの地図」を書きました。これには2つ理由があります。1つは、『売上の地図』がバージョン3に変わり、より簡潔になったので、それをしっかり出し直したかったこと。もう1つは、ありがたいことに色々な会社で『売上の地図』が作られるようになったのですが、カスタマイズをしない導入がすごく増えてしまったことです。
アイスクリームも掃除機も自動車も、全部同じ一つの地図に当てはめて考えようとしてしまい、「なんか全然しっくりこないな」と皆さんがモヤモヤしていました。それは、『売上の地図』が超高度に抽象化された、最大公約数的な図だからです。本来は、自社の業界、例えば「うちはアイスです」「ビールです」「車です」といった具体的なものにズームインしていく過程で、カスタマイズしなければいけないのです。
しかし、そのカスタマイズするという感覚があまりなく、全てのカテゴリーでそのまま使われ始め、みんながモヤモヤしていた。そこで、業界別にやり方が全然違いますよ、ということを示すために、カテゴリー別に『売上の地図』が違うということを解説したかったのです。
昔、AIDMAからAISASへ、という話がありましたが、これも全く同じです。「認知を獲得し、興味を持ってもらって、欲しくなってもらって、記憶してもらって、買ってもらう」というAIDMAは古い。インターネット時代は「検索(Search)」して「共有(Share)」するAISASの時代だ、となると、みんなAISASで設計し始めました。
しかし、スーパーで豆腐や牛乳を買う時に、事前に検索して買いに行く人なんてほとんどいません。それにもかかわらず、全ての商材の担当者がAISASで戦略を作り、「うまくいかない」「SNSで共有してくれない」と考えているわけです。歯磨き粉を使う前に検索する必要は少ないし、歯を磨いて「すげえ気持ちよくなったぜ」と共有する人もいません。
普通に考えれば、自社の商品には当てはまらない、「相変わらずAIDMAなんじゃないの」と考えるべきなのですが、どうしてもAからBだと言われると、みんなBをやり始めてしまう。なので、必ずカスタマイズが必要であると認識してください。
まず、カスタマイズでやらなければいけない最重要事項がこれです。マーケティングのやり方は、商品のカテゴリーによって大きく変わる、という話で、これは『売上の地図』全域に影響を与えます。
商品カテゴリーマトリクス:関与度と理性的/情緒的
これが昔から言っている「商品カテゴリーマトリクス」です。これはグラデーションなので、4つにバキッと分かれているわけではなく、10×10の100個のセルがある中のどの辺に位置しているのか、という感覚で捉えてください。
ここで強烈に理解すべきは、カテゴリーによって関与度は決まっており、企業の努力ではほとんど変えられないということです。下の象限は、スーパーやコンビニで売っているような値段が安い日用品、つまり一般消費財で、相対的に関与度が低いものです。「関与度が低い」とは、平たく言うと「別にどれでもいいかな」という感覚を持っているものです。
もちろん、その中でも一番お気に入りのものを買うのですが、買うにあたって厳密な情報収集や比較検討はしない、ということです。上は逆です。値段が高く、購入頻度が低いので、一度買って失敗すると後悔が長引きます。だから、買う前に徹底的に比較検討するし、レビューも読み込む。関与度が高い、ということです。
関与度が低い商品に、高い関与度を持ってもらうことを前提としたマーケティングをやっても、うまくいくわけがありません。例えば、関与度が低い調味料のウェブサイトをゴリゴリに作り込んで、いかに美味しいか、食材にこだわっているかを滔々と解説したところで、そもそもウェブサイトに来ないじゃないですか。
右と左も、マーケティング施策やクリエイティブレベルでアプローチが変わります。「理性的」に買うか、「情緒的」に買うかです。左下のガソリンは、近いか、入りやすいか、安いか、といった極めて理性的な理由で選ばれます。「どのガソリンスタンドに行くと楽しいか」「自分らしくいられるか」という感覚でガソリンを入れる人はいません。
右上は逆です。高級スポーツカーやハーレーダビッドソンなどは、燃費やスペックではなく、所有する喜びや、乗っている時に自分らしくいられるといった、気持ち的なもの、情緒的なものを求めて買われます。
『売上の地図』は、この4象限ごとに作られているわけではないので、皆さんが担当している商品がどの象限に入っているのか、そして、この『売上の地図』をどのようなレンズで見直さなければいけないのか、ということを強く意識する必要があります。歯磨き粉のマーケティングと、車のマーケティングは全然違うはずです。しかし、世の中で話題のマーケティング手法があると、みんなそれに飛びついてしまう。車の成功事例を歯磨き粉でやってもうまくいくのか、ということを冷静に考えなければいけません。
最寄品、買回品、専門品の違い、これがカテゴリー関与度の違いです。リスクが高いか低いかが一番大きな分け目です。リスクが高いから関与度が上がるし、リスクが低いから関与度が上がらない。購入頻度が高く、値段が安く、失敗してもリスクが低いから、いちいち買う前に検討しないのです。
「ヒューリスティック処理」と「システマティック処理」
ここで覚えておくと便利な言葉が「ヒューリスティック処理」と「システマティック処理」です。ヒューリスティック処理は、何も考えずに脊髄反射的に決めること。システマティック処理は、熟考することです。皆さんの商品がどちらで買われているかは、商品カテゴリーマトリクスの上下でほとんど運命が決まっています。ヒューリスティック処理される商材は、ヒューリスティック処理で選ばれやすいような施策を講じない限りヒットしません。
二重過程理論では「システム1」「システム2」という言葉で語られます。システム1がヒューリスティック処理、システム2がシステマティック処理です。我々は日常的にシステム1で生きています。システム2は体力を使うので、人間はできる限りシステム1で生活しようとします。過去の知識や経験、習慣に基づいて、「大体これを買っておけば間違いない」と決めるのです。
保険に入ろう、家を買おう、掃除機を買い換えよう、という時に、一瞬脳はいつも通りシステム1で処理しようとしますが、「いや、掃除機を買ったのは7年も前で、最新のものが分からないし、どれを買えば後悔しないか判断できない。仕方ない、ちゃんと情報収集して決めよう」と、しぶしぶシステム2が発動される、という感覚です。
人間はできる限り燃費良く生きようとする生き物なので、脳が一番カロリーを消費する「思考」を避けるため、過去の知識や経験に基づいて瞬発的に直感で選ぼうとします。スーパーで皆さんが0.5秒から1, 2秒で商品をカゴに入れているのは、全部システム1で意思決定しているからです。
システム2の方は、カロリーを消費しながら考えることを多くの人がするので、自社の商品の特徴を理解してもらう、世界観を知ってもらうためのコミュニケーションは刺さりやすいです。しかし、システム1はそんなことを求めていないし、してくれない。うっすら入っているもので直感的に買われる宿命にあるのです。
ベネフィットの3分類
もう一つの軸、横軸の話です。これを理解するためには、デイビッド・アーカーの「ベネフィットの3分類」が分かりやすいです。
- 機能的ベネフィット: 商品サービスを使うことで得られる物理的なメリット。歯医者を選ぶ時の「行きやすさ」「施術の上手さ」などです。
- 情緒的ベネフィット: 商品を使うことでどんな気分になれるか。ハーゲンダッツを食べる時の「頑張った自分へのご褒美」という気分です。
- 自己実現ベネフィット: その商品を持つこと、使うことで、自分らしくいられる、自己実現が満たされるという感覚。ハーレーダビッドソンに乗る時の気分がこれにあたります。
自社の商品が、どのベネフィットを一番お客さんに期待されて買われているのかを、冷静に考える必要があります。
「良い商品」の定義は、人によって、カテゴリーによって全く違います。同じアイスクリームでも、MOWは「この値段でこんなに美味しい」という物理的なベネフィットとコストパフォーマンスで選ばれ、ハーゲンダッツは「ご褒美」という情緒的なベネフィットで選ばれます。歯磨き粉だって、虫歯予防なのか、ホワイトニングなのかで「良い商品」の定義は変わります。軽自動車とスポーツカーも、人によっては軽自動車の方が「良い車」かもしれません。皆さんも自分の頭で考えなければいけません。自社の商品は一体どのポジションで、どんなベネフィットなのか、ということです。
【結論1】マーケティングのやり方は、商品のカテゴリー(関与度の高低、理性的か情緒的か)によって全く違う、ということです。
原則2:全てのお客さんが「今すぐ客」ではない
多くの人は、なぜか自分の商品サービスを買ってくれるお客さんは、全て「今すぐ客(レディな状態)」だと考えがちですが、そんなことはありません。これも『売上の地図』全域に関わる話です。
「今すぐ客」と「そのうち客」の市場構成
家の歯磨き粉がなくなったら、必ず買い替えますよね。常にニーズが顕在化している「今すぐ客」です。では掃除機はどうでしょう。家の掃除機が壊れた時や調子が悪くなった時に「買い換えるか」となりますよね。買い換えてから5年から7年間は、ニーズは潜在期に入ります。その人に新しい掃除機を勧めても「この前買ったばかりだからいい」となります。当たり前の話です。
皆さんの商品が属しているカテゴリーの特性として、「今すぐ客」と「そのうち客」がどういう構成になっているのか。これはカテゴリーによって宿命として決まっています。スーパーやコンビニで売っている商品は、ほとんどが「今すぐ客」しかいない市場です。一方、マトリクスの上、関与度が高い商品は、一度買ったら、引っ越しなら2〜4年、車なら5〜10年、保険ならしばらくは買い替えません。つまり、「そのうち客」が膨大にいるマーケットなのです。
関与度が高い商材の場合、「今すぐ客」の30倍もの「そのうち客」がいるマーケットで売上を作っていく、という考え方が必要です。しかし、皆さんは12ヶ月の会計年度でどれだけ売れたかをコミットしなければいけないので、どうしても「今期、今期」と考えがちです。
しかし、今期、日本で売れる掃除機の台数はもう決まっています。企業の努力で販売台数は増やせません。例えば、5500万世帯あって、10年で壊れるとすれば、年間550万台が売れる市場規模です。これが「今すぐ客」のマーケットサイズで、これを競合と殴り合って取り合っているのが実態です。
「そのうち客」へのアプローチが競争優位に繋がる
しかし、来期になれば、また来期に掃除機が壊れた人のニーズが顕在化します。そして、5年、7年と掃除機のことなど考えたこともなかった人が、壊れた瞬間に「ダイソン」と検索したりします。なぜ、ニーズが顕在化した瞬間にそう検索するのか。それは、ダイソンがずっと「そのうち客」に対するマーケティングにお金と時間をかけ、いつかニーズが顕在化した時に真っ先に思い出してもらえる「第一想起」のポジションを取っていたからです。
今の競争は、「今すぐ客」のところでみんながしのぎを削っていますが、もう限界に達しています。CPCはどんどん上がり、効率は低下するのは当たり前です。市場のサイズは変わらないのに、みんなが「今すぐ客」にお金と時間を突っ込んでいるからです。
これから差がつくのは、「そのうち客」に対してどれだけしっかり時間とお金を使い、想起集合の中に入れるか、ということだと思っています。「今すぐ客」の獲得競争は、負けないために絶対にやらなければいけません。しかし、勝つためには、それに加えて、いかに「そのうち客」の育成ができているか。これが競争優位になります。
デジタルマーケティングの施策は、基本的に左側、つまりニーズが顕在化した人を効率的に刈り取ることに寄っています。各社がデジタルシフトを進め、右側の予算を左側に突っ込んでいるので、効率的な収穫合戦になっているわけです。これは悪いことだと思います。昔の、一見非効率に見えるテレビCMのような施策が、じわじわ効いて認知や好意を向上させ、ニーズが顕在化した時に真っ先に思い出してもらえるポジションを獲れていた、というのもまた事実です。
私の提案は、左側に100%お金を使っているうちは、ずっとレッドオーシャンで収穫を競う勝負しかできません。10%でもいいから右側に、つまり「そのうち客」の育成にお金を使っていかない限り、どんどんジリ貧で辛くなるだけです。なぜなら、皆さんのデジタルマーケティングのCPAやCPCも、どんどん悪化していっているはずだからです。みんなが同じことをやっているからです。
BtoBにおける「そのうち客」育成の重要性
BtoBも同じです。我々トライバルメディアハウスもBtoBの会社ですが、マープスのような活動をしていると、「ご褒美コンバージョン」として、トライバルメディアハウスで指名検索をして、いきなり問い合わせをしてくれる方が何件もあります。これは、ニーズが潜在期にあるうちから、「トライバルさんはこういうことに詳しい会社なんだな」という理解や信頼がすり込まれているからです。
クライアント企業のニーズを我々の営業努力で顕在化させることはできません。BtoBは、いつどのお客さんのニーズが顕在化するかコントロールできないのです。だから重要なのは、3ヶ月後か1年後か、ニーズが顕在化した時に、一番最初に「トライバルさんに相談してみようかな」と思い出してもらえるかどうか。そうなれば勝ちです。
これは、掃除機が壊れた時に多くの人が「ダイソン」と指名検索するのと全く同じメカニズムです。「そのうち客」をしっかり育成しておくと、ニーズが顕在化した時に真っ先に思い出してもらい、結果として「今すぐ客」を収穫できるのです。
【結論2】全てのお客さんがレディな状態ではありません。特に関与度が高い買回品や専門品は、膨大な「そのうち客」とごく一部の「今すぐ客」で形成されています。なので、戦略を立てる上で、両者にどれぐらいの資源を配分するかが極めて重要な意思決定になります。
原則3:売上は「想起」と「売場」で決まる
メンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティ
横文字にすると「メンタルアベイラビリティ」と「フィジカルアベイラビリティ」です。『売上の地図』のど真ん中にあるこの2つが、売上に影響を与える最重要変数です。20個の変数の中で重要なものだけを抜き出すなら、この2つです。これに尽きます。「真っ先に思い出してもらえるか(想起)」と、「買いたい時に買いやすい状態になっているか(売場)」です。
ストア・カバレッジとインストア・シェア
一般消費財の場合、1店舗でも多くのお店に商品が置いてある状態(ストア・カバレッジ)が、最も売上が上がりやすい状態です。また、一つの店舗の棚の中で、自社の商品がどれだけのスペースを占めているか(インストア・シェア)も重要です。
「想起」と「買い求めやすさ」、どちらがどれぐらい重要かというと、商材によりますが、特に一般消費財は70%が「買い求めやすさ(フィジカルアベイラビリティ)」で決まります。極端な話、広告を一切打たなくても、棚に置いてあれば売上は上がるのです。その逆はありません。どんなに想起されても、売場になければ買えないからです。
もちろん、家電のようにEC化率が40〜50%まで来ている商材であれば、Amazonや楽天といった「デジタルシェルフ」での買いやすさも重要になってきます。これも商材によって柔軟に考えてください。
【結論3】売上は「想起」と「売場」で決まる。この2つが最重要変数です。
原則4:認知ではなく「想起」が重要
皆さんの多くは広告やPR、デジタルマーケティングの担当者だと思うので、売場(営業部の仕事)よりも、自分たちの仕事として重要なのは「想起」を上げていくことです。これに尽きます。
ブランドヒエラルキーと「想起集合(エボークトセット)」
重要なのは「認知」ではなく「想起」です。ほとんどのブランド調査で取られている「認知度」は、「助成想起」(商品を並べて知っているものにチェックを入れてもらう)です。しかし、しのぎを削る競争の中で選ばれるのは、「言われてみれば知っています」というレベルの商品ではありません。ニーズが顕在化した時に「真っ先に思い出してもらえるか」で勝負が決まっています。なので、『売上の地図』では「認知」ではなく「想起」を重視しています。
ブランド・ヒエラルキーで言うと、トーナメント戦のようになっています。まず「知名集合」。知らない商品は買われないので、知られていることは大前提として重要です。しかし、スーパーの棚を見れば分かりますが、「知っているけど買ったことはない」商品がほとんどです。つまり、認知されているだけでは買ってもらえません。次に「処理集合」。知っている上で、ある程度商品の特徴を理解してもらえているかどうかがここです。
そして最重要が「想起集合(エボークトセット)」です。P&Gのような外資系企業はこれをめちゃくちゃ重要視しています。なぜなら、ここに入っていなければ、明らかに買ってもらえないと分かっているからです。想起集合とは、ニーズが顕在化した時に何も見ずに頭に浮かぶ、好意的な選択肢の集合体で、およそ全カテゴリーで3つ以下しか入っていません。
「ビールといえば?」「ポテトチップスといえば?」と聞かれて思い浮かぶものが想起集合です。大体、カテゴリーシェアNo.1のブランドが第一想起されます。これは「ダブル・ジョパディの法則」で説明できます。シェアが高いから第一想起されるし、第一想起されるからシェアが高くなる、という両方の因果関係があるのです。
想起集合には、多くても3つしか入りません。「掃除機といえば?」と聞いても、平均1.87個しか出てこないのです。そして、人は基本的に最初に思い出したものから検索して調べ始めます。我々の調査でも、想起集合に入っていない商品の売上は低く、第一想起、第二想起、第三想起の順に売上は下がっていきます。超極論を言うと、売上は想起と強い相関関係にあるので、売上を上げたいなら想起を上げればいい、ということです。
想起集合に入れなかった惜しいブランドは「保留集合(ホールドセット)」に入ります。もし皆さんの商品がここなら、マーケティングの最重要課題は想起集合に入ることです。「拒否集合」は、「知っていて、理解した上で、絶対に買いたくない」と思われている状態です。ここに入ると復活は難しく、一度市場から撤退して名前を変えて再参入する、といったことが必要になります。入る理由は、自分自身の最悪なブランド体験か、身近な人からの悪い口コミです。一番有利なのは「第一想起」の獲得です。
ファネルと想起集合の関係
この「想起集合」という概念と、マーケティングでよく使われる「ファネル」というフレームは、この図で見事に合体します。認知を獲得することは大事ですが、それは助成想起に過ぎません。比較検討される、つまり想起集合に入らないと購入には至らないのです。認知の「量」だけでなく「質」を高め、純粋想起、想起集合、そして第一想起へと進めていく必要があります。
来週詳しく説明しますが、私が使っているファネルマップの上部にこれを追加しています。認知の質を高め、左から右へお客さんを移動させていくことが大事で、そのためには各段階に効く施策が必要です。一つの施策で一気に移動させることは難しいのです。
未来のお客さんを育てるマーケティング
ニーズが顕在化したお客さんを効率的に刈り取るデジタルマーケティングばかりやっていると、未来のお客さんを育てていないことになります。アメックスが、デジタル施策で効率的にカード申込者を獲得し続けた結果、5年経ってブランドの指名検索数が激減していた、という話がありました。これは、「いつかカードを作るならアメックスがいいな」という人を増やす活動をしてこなかった結果です。
指名検索は、最も効率的にお客さんを獲得できる最強の入り口です。なぜなら、それは過去にお金を投下してお客さんを育て終わった結果だからです。だから、バランスが大事なのです。
JALのInstagramが素晴らしいのは、この点を理解しているからです。365日のうち364日は飛行機に用がない人たちに、毎日「チケットを買え」と言っていたらブロックされて終わりです。いつか飛行機に乗るというニーズが顕在化した時に「JAL」と検索してもらうために、常時接続の関係を作り、少しでもブランドに触れてもらう。そうして半年、1年と関係を築いた結果、ニーズが顕在化した時に指名検索してもらえれば勝ち、という考え方です。なので、公式アカウントの効果測定指標は、売上ではなく、想起率、好意度、利用意向の3つなのです。
【結論4】一番売れている商品は、真っ先に思い出されている商品です。
原則5:想起されるかは「プレファレンス」次第
想起の源泉としてのプレファレンス
「想起」が大事なのは分かった。しかし、この「想起」も出力なのです。想起を上げるためには、何らかの入力をしなければいけません。その入力が「プレファレンス」です。プレファレンスという力が上がることで、結果として想起が上がるのです。
プレファレンスを構成する3要素:「価格」「ブランド」「製品パフォーマンス」
では、プレファレンスを上げたい。このプレファレンスは、「価格」「ブランド」「製品パフォーマンス」の3点セットで上がったり下がったりします。つまり、この3つをコントロールする必要があるのです。
プレファレンスとは、USJを再建した森岡さんが言うように、「サイコロを転がして自社の商品の目が出る確率」のようなものです。コンビニで水を買う時、我々は毎回サイコロを振っている。いつも同じ水しか買わない人は、毎回必ずそのブランドの目が出ている、最強の状態だということです。この確率をどれだけ上げられるかが、プレファレンスを上げることです。
このサイコロの目が出る確率を上げるためには、「価格」「ブランド」「製品パフォーマンス」の3つが影響します。価格は、一般的には低いほどプレファレンスは上がります。
ブランド連想の重要性
ブランドは、アーカーが言う4つの要素、「ブランド認知」「知覚品質(良い商品だと思われているか)」「ブランド・ロイヤルティ(また買いたいと思われているか)」、そして「ブランド連想」です。この中でも「ブランド連想」がすごく重要です。
自社の商品やサービスがどんな連想を持たれているか。「鳥取といえば?」と聞くと、ほとんどの人が「砂丘」と答えますが、それ以外はなかなか出てこない。これは連想に厚みがないということです。一方、「北海道といえば?」と聞けば、ラーメン、パウダースノー、チーズなど、色々出てきます。連想が豊かで厚みがあるから、北海道は観光客が多いのです。プレファレンスを上げるためには、この連想がとても大事です。
製品パフォーマンスとカテゴリー関与度の関係
当たり前ですが、製品パフォーマンスも重要です。私は頭痛薬を買う時はいつも「バファリンプレミアム」一択です。なぜなら、いつも飲んでいて、すぐに頭痛が引くという絶対的な信頼を置いているからです。この製品パフォーマンスへの高評価がプレファレンスを押し上げ、第一想起に繋がり、購入に至っているわけです。
これをカテゴリーマトリクスで考えると、ペットボトルのお茶のようなヒューリスティック処理で買われる商品は、買う前に考えないし、飲んだ後も厳密な評価はされません。一方、頭痛薬のように、効能効果を待ち構えている商品は、パフォーマンスが厳密に評価されます。なので、関与度が低い商品よりも、関与度が高い商品の方が、製品パフォーマンスがプレファレンスに与える影響は大きい、ということです。
【結論5】売上を上げるためには想起を上げる必要があり、想起を上げるためにはプレファレンスを上げる必要があります。そして、プレファレンスは「価格」「ブランド」「製品パフォーマンス」の総和によって作られます。
まとめと次週の予告
じゃあ、プレファレンスを上げたい、となるのですが、このプレファレンスもまた出力なのです。プレファレンスを上げるためには何の入力をしたらいいのか。それが、広告、PR、ソーシャルメディア、オウンドメディアといった「PESO」です。この4つの入力によってブランド価値を上げ、プレファレンスを上げ、想起が上がるから売上が上がる。そういう考え方になります。
この話は来週になります。来週は、PESOモデル、真実の瞬間、そしてファネルマップの話をします。
今日のまとめ
- 売上は、全経営活動の出力であり、広告宣伝部の出力ではない。
- 売上は、因果の「構造」でできている。
- 商品のカテゴリーによって、マーケティングのやり方は全く違う。
- 関与度が高い商品の場合、全てのお客さんがレディな状態ではない。
- 最重要変数は「売場」と「想起」である。
- 想起を上げるためには「プレファレンス」が大事。
提出義務のない宿題と各種案内
今日の提出義務のない宿題です。興味がある方はぜひやってみてください。皆さんが担当している商品の売上に影響を与えている変数を、コミュニケーション以外のものも含めて全部出してみてください。余裕があれば、それを矢印で繋げてみる。同僚とやると、めちゃめちゃ良い発見ができると思います。
YouTubeチャンネルもやっていますので、ぜひ通勤中などに耳で聞いて、体に染み込ませてみてください。キャリア相談も受付中です。求人情報も公開していますので、ぜひ覗いてみてください。
ということで、今日の講義はこれにて終了です。ぜひ来週も連続で聞いてください。お疲れ様でした。さようなら。