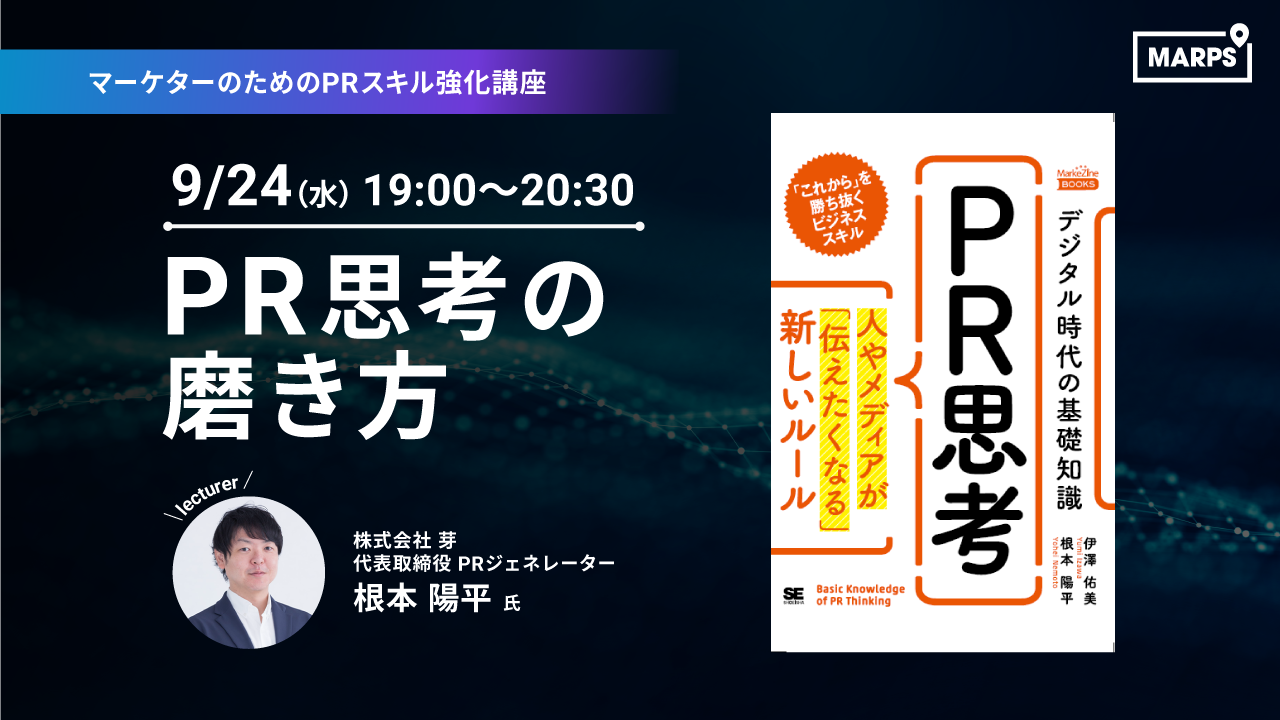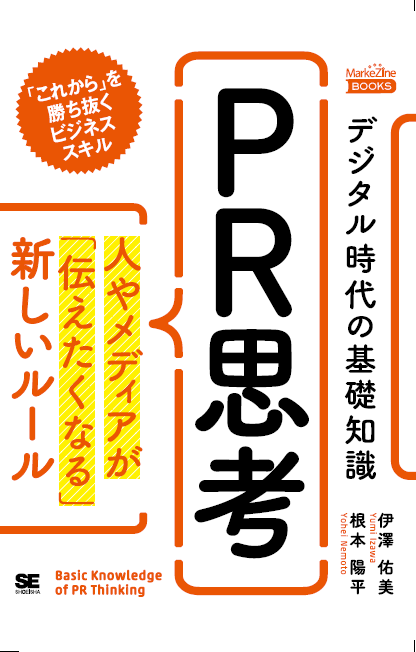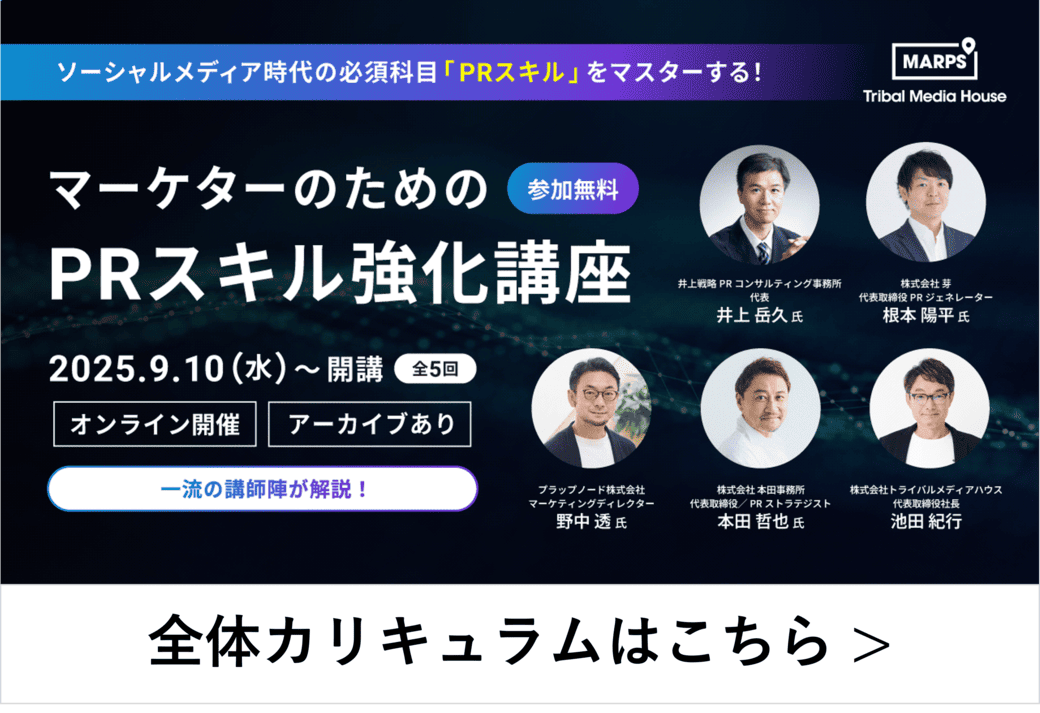イントロダクションとPR思考の重要性
※このテキストは『マーケターのためのPRスキル強化講座② PR思考の磨き方』の書き起こしです。文中の登壇者名表記は敬称略。
池田:はい、皆さんこんばんは。今週も始まりましたMARPSでございます。前回からお届けしているマーケターのためのPRスキル強化講座、今日で2回目ですね。PR思考の磨き方という項目で、根本さんにお話いただきます。
この講座の次はAI時代のPR、10月22日が第3回目となりますのでご注意ください。
今回のこのPRスキル強化講座の中でも1番と言ってもいいかもしれません。重要なのがこのPR思考なんですね。いろんなテクニックとか技法とか色々あるんですけども、とにかくこのPR思考というものが、とにかく難しい。
ペイドメディア中心のマーケターが抱える課題
この講座の告知のためにノートを書きましたけれども、これがPESOの図ですね。前回の井上さんの講義でも出てきましたし、僕もノートで書いてますし、今日根本さんの講義でもPESOってのは出てくるんです。このデジタルマーケターの場合、かなり多くの人たちがこの左上のペイドメディア、つまりデジタル広告、運用型のいわゆる刈り取り型の広告に、従事をしている方々の、比率っていうか人口がまず1番大きいわけです。
その次に右下のシェアードメディアの、SNSに関連するお仕事をされていらっしゃる方々で。次に、デジタルマーケティングという括りではたまに、語られたり語られなかったりするメディアの左下のとこですね。デジタルマーケティングに従事してますっていう方の中で右上のメディアの仕事に従事をしているというか、やってる方っていうのはもう僕の知る限りでも相当少ないですよね。
特に左上のペイドメディア、デジタル広告、運用型、いわゆる刈り取り型をやっていらっしゃる方々からすると基本的に全てがコントローラブル。自社でコントロールすることができます。広告の特徴でいつも言ってるやつですよね。自社が出したい時期に出したいメディアで出したいクリエイティブで出したいだけ出すことができるのがペイドメディアなので。
このアーンドメディアっていうのは、前回の井上さんの講義でもありましたが、コントロールできないんだと。全て出すか出さないかってのはメディアの方がその向こう側にいる視聴者や読者の方々に有益だと判断をすれば出してくれます。出ない場合は出ないということですね。
なので今日の根本さんのお話のど真ん中にある社会の人たち、読者や視聴者の方々ないしはそれを代表するメディアの方々が何に興味を持つのかということ、自社でコントロールできない領域のことをPR思考で考えなきゃいけないんですけど。
このペイドメディアで日々自社でコントロールすることができる範囲で、仕事をずっと長年やってきていると、広告に関して何をどういうクリエイティブで表現すると、どれぐらい反応があるのかみたいなところはめちゃめちゃ皆さん鍛えられるんですけど、その逆のこのメディアのところのPR思考と言われてるものに関しては、びっくりするぐらいなかなか鍛えられないんです。
僕もこのPRに隣接する領域での仕事を長らくやらせてもらっていますが、広告脳で死んでいる方がこのPR思考っていうものに脳の筋肉っていうかその思考のパターンを切り替えていくためにどう頑張っても3年から5年ぐらいかかる感覚なんです。それぐらい広告脳として染みついている筋肉の使い方とか思考のパターンみたいなものとこのPR思考と言ってるものというのはすごく簡単そうに思えてめちゃくちゃ難しいんです。
なのでこのPR思考というものをこの特にマーケターがPRを学ぶ上ではめちゃめちゃ重要であるということで。第2回目に根本さんに来ていただいたという背景があります。
どうやったらデジタル時代にPRうまくやれるのかみたいな話の前にですね、デジタルマーケターの方々は、このPR思考というものをどれだけ鍛えることができるかっていうところがめちゃくちゃ重要になります。ということでこの本の著者でもある根本さんにお越しいただいています。
(中略:根本さんの経歴紹介とMARPS講座の構造説明)
今回はマーケターが学ぶここら辺ですね、パブリシティとか、隣接するところで戦略PRとか、ここら辺のことを仕掛けていく上で。重要なPR思考、PRとしての考え方ですね、を学んでいただくという会になります。
私の前説これぐらいにして、今から根本さんにご登場いただき、およそ70分から75分ぐらい、8時15分から20分ぐらいまで、お話いただいて最後10分質疑応答で8時半に終了という流れになります。では根本さんお願いします。
PR思考の定義と広告思考との違い
根本:はい。よろしくお願いします。根本と申します。本日2回目ということで、1回目に「そもそもPRとは」という話はしていただいたということなので、今日私の方ではPR思考の磨き方というところですね。今日から使えるマインドのスイッチャーと言うんですかね、マーケターの自分と、PRの自分とか広告プランナーの自分というのをどういう風にスイッチングしていけばいいのかを今日お話しできればと思っております。
(中略:聴講者のPR関与度アンケート)
根本氏の自己紹介
改めまして根本陽平と申します。今株式会社芽という会社で代表をやっておりますが、並行して東京都武蔵野市の広報戦略アドバイザーとして週1勤務をしております。約1/5ですね。5分の1公務員ぐらいの感じではあるんですけども、あとはPR論、パブリックリレーションズ論というものを、大正大学というところで非常勤講師をしております。
普段は企業や団体そして自治体さんのPR広報というか、機能を、半分外の人間なんですけど、内部に入りながら、PRプランだけじゃなくてノウハウを納品するというコンセプトで今やらせていただいております。それまでは電通PRコンサルティングというところで、ずっとやっておりました。
やはりマーケティング及び、統合コミュニケーション、IMC、そして広告、マーケティング領域をかなりやってきた上でそちらに非常に関わっているというところなので、今回マーケターのためのということで、これまでの経験で皆様にご提供できるものがあればということで多分池田さんからご依頼いただいたのかなという風に思います。
(中略:池田の書籍についての言及)
PR思考とは「第三者視点での発想」
PR思考なんですけども、このように定義させていただいております。世の中(第三者)視点で発想する行為と。つまり自分から見た景色ではなく、他者側から見た景色で思考するという行為でございます。なのでスイッチングが必要です。
PR思考ワークショップと事例分析
ワーク:大学新聞の見出し作成
早速なんですけども、ちょっとワークをやってみたいと思います。考える時間は丸1分でございます。1分でパッと見ていただいて、これ皆さんのお手元でワードなりメモなり手書きなり何でも結構ですので書き止めていただけたらなという風に思うんです。
(中略:ワーク内容の説明と解説※ワークについてはアーカイブ本編を御覧ください)
事例:武蔵野市の広報誌での見出し変更
例えばこのようなことも1つの事例かなと思うんですね。市の広報誌で多文化共生・交流課さんの市民交流ツアーっていうもののPRとして。市報に記事を載せたというようなことなんですけど。武蔵野市は山形県酒田市と岩手県遠野市と交流ツアーっていうのを開いているんですね。実はちょっと定員割れしちゃってますというような課題がありました。
ここで何やったかと言うと、こういう感じで変えたんですね。例えば右側「風情ある港町で旬の味覚と歴史を楽しむ旅、山形県酒田市への市民交流ツアー」ということで1つ枕言葉を足したんですね。それまでは市民交流ツアー、酒田市への市民交流ツアーっていうそのファクトそのものしかなかったんですけど。知らない方はこれがどういう自分にメリットがあるのかっていうのは分からないですよね。
なので、他者の視点、他者の景色から考えた時にこの1行、「あ、そうすると歴史や味覚楽しめるんだ」って思う。この1行、これ僕は補助線コピーって呼んでるんですけど、この補助線を足しました。そうしたところですね、なんと他の施策はそんなに変わってないんです。なんですけど、このタイトルのコピーと写真を工夫しただけで定員割れが解消して新規の申し込みの反響を得たというようなことがありました。
改めてPR思考は自分の景色じゃなくて他者から見た景色です。違う言い方をすると見せたいものじゃなくて見たいものですね。意識的にあっちから考えるという筋力を育てましょう。そして意識的にあっちにスイッチングしましょう。それがPR思考のポイントかなという風に思います。
PR思考の土台:ベン図分析と「同じを見つける」力
ベン図分析による「手を取り合うポイント」の探求
PR思考の整理の時にこのベン図を使います。左側は企業やブランド、自分が担当している主体者。で、あっち側は世の中ですね。世の中の問題・関心。この手を結べるポイント。PRは良い関係作りとか、パブリックリレーションズっていう教科書的にはそういう風に書いてると思うんですけど。実務家として何をするかということは手を結べるポイントを探る。そういった行為かなという風に思います。
事例:IKEAの「ThisAbles」プロジェクト
イケアさんのビジョンは「より快適な毎日を、より多くの方々に」というビジョンを掲げておりました。一方で、世の中側の問題は、量産家具は1割の方には不向きで、フィットしないという現象が起きる。先ほどの障害者の方々とかですね。生活において基本的な行動が困難な対象になる。
行ったのは、家具に付けるパーツをつくること。家具自体を特別なものに変えるんじゃなくて、家具はそのまま。ただしパーツ、1個付けると機能的になるってものを3Dプリンターで作れるようにデータを配布して、各店舗で作れるようにしたというようなプロジェクトですね。で、これを「ThisAbles」。「これならできる」というプロジェクトにしました。
このように自社が掲げるブランドのミッションと、その世の中が抱えてる問題とどうしたら手を結べるか。この辺はすごくPR思考っぽいなという風に思っております。
事例:日本花き振興協議会の「母の月」プロジェクト
私が携わったのは日本花き振興協議会。お花の需要拡大をやっている団体なんですけども。行ったのはですね2020年ですね。コロナで外出が禁止になったわけですよね。お花屋さんからすると母の日が控えてるわけです。
この時着目した世の中の問題は、母の日に送りたいんだけど、やっぱりすごい込み合ったりして。お客さんも込み合った店舗に行きたくないし、店員さんも怖いし、あと流通も逼迫してるっていう。
そういった3者のステークホルダーが、どうにかならないものかと言ってるのに対して、母の日って1日だけじゃなくて母の月、いつ送ってもいいよ。そしてカーネーションじゃなくてもいいよ。そんなような呼びかけを行ったんです。そういった形で、自分たちと世の中の接点、世の中の問題関心の接点を見つけていく。そのような行為をPR思考という風に呼んでいます。
広告とPRの思考の違い
ズバリですね、PRは同じを見つけるのが得意っていう風に思うんです。例えば広告は、違いを見つけるのが得意ですよね。ポジショニング。ホテルとはどう違うんだ。旅行パッケージはどう違うんだ。宿泊サイトとはどう違うんだ。その違いを見つけて、それを、ホテルや他のサービスにない価値を提供してデジタル広告とかでコピーで当てたりするわけです。
じゃあ、PRは一方何かと言うと、さっきの手を結べるところを探すっていうのがPRの思考なので、自分たちと世の中がどこかで手を結べないのかというところですね。例えば、自治体さん、空き家対策。空き家がすごく増えてるという社会問題がありますよね。その一手としてこの民泊プラットフォームってどうですかっていう形で同じところを見つける、同じを見つけるっていうようなことを思考するというのがPRの特徴かなという風に思うんですね。
情報価値を高めるフレームワーク「PR IMPAKT®」
これが今日多分1番のメインメソッドかなと思いますけども、情報価値を上げる視点「PR IMPAKT®」というところにお話を移していきたいと思います。
メディアが注目する6つの視点(IMPAKT)
この手を結べるポイントを探すっていうのは、本質的にはメディアリレーションだと言われているんです。このステークホルダーに一気に1度に一斉に情報が届けられる。しかもそれが中立的立場で信頼性のある情報で届けられるっていうことで。メディアから語っていただくというのが非常に機能するよ、と。
Think Like a Publisher(邦題:〜編集者のように考えよう〜 コンテンツマーケティング27の極意)という本もありますが、編集者のように考えてみよう。というところがお話のポイントです。そこで、このPR IMPAKT®というようなフレームワークで考えてみることを提案します。PR IMPAKT®は IMPAKTっていうのがKにもじった頭文字になってます。
Inverse、Most、Public、Actor、Keyword、Trendです。報道論調分析の結果、この6つの視点が大事なんじゃないかという風に作られたものです。
視点1:情報の強度(InverseとMost)
- Inverse(意外性、逆説)構文で言うと「まるまるなのにバツバツ」みたいなギャップ。皆さんが想像している世の中的な固定概念というか既成事実が裏切られた時に、Inverseというのが発揮されてそれがニュースバリューに直結する。
- 例:泊まれる水族館(水族館は普通泊まれない)、おにぎらず(おにぎりなのに握らない)、ZONeの広告(広告は普通見せたいのにあえて見えづらい)。
- Most(最上級表現、1番)最上級表現。世界一高いビル。ただ「◯◯◯な第一想起を狙う」っていうのが、Mostのプランナー的な考え方です。世界一高いビルじゃなくても何かこの領域だったらMostなんじゃないのっていうような切り口。
- 例:日本初の無人AIコンビニ(第一想起を狙う)、静岡市のプラモデル(プラモデルの出荷量でMostをプッシュ)、世界最小広告(小さいこともMostになり得る)。
視点2:説得力の強度(ActorとKeyword)
- Actor/Actress(人、キーパーソン)何を言うかもすごい大事ですけど、それが誰が言ってるか。コツとしてはその人がどんな文脈をまとっているかということを見極める。フォロワー数より纏っている文脈。この文脈とは、本人と他者(それ以外の他者)の間で共有されている暗黙の人格、暗黙の背景です。
- 例:内村航平選手はブラックサンダーが大好き(超人アスリートがチョコレート好きという文脈)。
- IMPAKTっていうのは何個あってもいい。ActorがInverseなことするとか、ActorがMostなことをする。
- Keyword(みんなが使いたくなる愛称)母の月とか、その一言で言っただけで初めて聞くんだけど意味が分かる。洗練された初めてのワードよりもこうみんなが使いたくなる愛称が非常に大事。1歩先よりも半歩先くらいのイメージ。
視点3:時代の強度(PublicとTrend)
- Public(社会性、公共性、地域性)メディアはやはり社会性のあるものを届けるために存在する。企業の営利目的だけだと記事は書けない。それが社会にインパクトがあるとかすごい公共性があるものだったら取り上げなきゃって思うわけです。
- Trend(時流、季節性)時流、トレンド、季節性。バレンタインや母の日などの季節的な話題も含む。時代の気運を味方につけて必然性を強化しよう。なぜそのプロジェクトを今するのかっていうのに必然性が欲しい。
- 例:廃校(社会性がある)、宮崎県小林市のシムシティ課(地方創生という社会課題)、だんごむしのガシャポン(6月4日の虫の日に発売)。ニュースになってないものって今やる必然性が弱いものなんですよ。
企画者のためのPR IMPAKT®活用法
プランナー、企画者は仕掛け人。
- 5W1Hを上下左右にずらしてみる:5W1Hの何かをフォーカスしてずらしてみると、それはニュースバリューに直結する。Inverse(意外性)がつき、初めて見ればMostになる。
- 既存資産を見つめ直す:フォロワー数よりActorの文脈。社長とか研究者とか、既存の持っている既存資産をまず見つめ直して、そのActorがInverseしたりMostするってどういうことか考える。
- みんなが使いたくなる愛称を見つける:みんなが使いたくなる愛称を世の中に出す前に探す。ゾンビ臭のように、NHKの「あさイチ」でも出るような概念自体は普及する。
- 最も賛成しやすい日を見つける:365日のうち最も説得力があり、みんなが賛成しやすい日はいつかを考える。制作スケジュール上ここがローンチだよねってことじゃなく、この日だからこそこの企画が光るんだという必然性を強化する。
実務:プレスリリースへの応用
プレスリリースの見出しをまず作るんですけど。ここにPR IMPAKT®チェックをするんです。InverseとMostあるかな。Publicで言うと何を、何に対する問題解決なんだろう。Actorいないかな。必然性が高められる日はないかなって感じでPR IMPAKT®でチェックする。Amazonさんが新規事業や企画会議の時にプレスリリースから作る、プレスリリースから考えようっていうのをやっています。
PRの多面的な発想:マルチコンテクスト
いい企画は様々な顔を持つ。マルチコンテクスト、つまり複数の切り口、複数の文脈を持っている。
マスメディアっていうのもかなり組織化している。機能的に縦割り組織。例えば新型コロナ感染。政治系の記者は法律や予算。文化系の記者は中止になったライブ。同じテーマなんだけど守備範囲によって切り口が全然違う。
いかに自分たちのプロジェクトがこのメディアにはこういう顔つき、このメディアにはこういうところが面白いんじゃないかっていうのを、それぞれ細分化して複数の切り口を持つ。という風に考えようというのがPRの思考なんです。
広告は1点突破がより強くないと刺さらない。PRでいくとマルチコンテクスト。ファクトはそのまま。取り上げていただくのはメディア側。メディアの皆さんが料理しやすいようにいろんな顔を持つ。PRの多面的な発想です。
情報優位な状態を作る
そうすることによって、競争優位な状態とは別に情報優位な状態というのが作っていける。例えばチョコレートメーカーB社(1位じゃない会社)がバレンタインに関してはめちゃくちゃ調べていて、「男女逆転が起きてる」「ギリチョコって古いらしい」といった情報を持ってるとしたら、メディアはA社じゃなくてB社に取材したいですよね。
企画者のためのマルチコンテクスト活用法
自分たちがそれぞれのメディアでどう語れるか想像してみましょう。
- 泊まれる水族館で言うと、ビジネスメディアだったら「水族館の夜ビジネスに注目」。グルメで言うと「夜の水族館限定の青いグルメが話題」など。
- それぞれのメディアさんがどういう風にこのプロダクトや施設を魅力的に見ていただくんだろうということを想像してこれを最初から設計する。
- 流行語大賞とかそういうものを取るようなものって必ずマルチコンテクストになってます。
- マルチコンテクストを、戦略的に作っていく。それには自分1人よがりじゃなくて他者から見た窓をたくさん持つ。
- この1個1個にPR IMPAKT®を当ててくんです。細分化してPR IMPAKT®を当てていく。これで必ず打率が上がっていくと思います。
PESOモデルと情報流通構造
広告の「投下型」とPRの「流通型」
広告はやっぱり投下型だと思っています。コントロールができてそこに一斉に攻勢をかけられる。PRは、アーンドメディア、特に自分たちがコントロールできないアンコントローラブルなメディアです。他者に編集権やタイミングのジャッジがある。
ただ、何か1つメディアに乗りました。Yahoo!トピックスに上がりました。会話されたらトレンドに上がりました。どんどん情報が雪だるま式に流通していく。波紋のように広がっていく。このPESOを全体で設計するっていうのが非常に重要。
思考のスイッチングを伴うPESOの2分割
僕の場合これを2分割するっていう考えをお勧めしています。ペイドとオウンドで分ける。アーンドとシェアドで分ける。
このペイドとオウンドっていうのは主語が自分。自分が語る。アーンドとシェアドは主語主体が別にいる。誰かに語られるので主語が違うんです。OとPは最終決定自分。EとSは最終決定は他者。この圧倒的な出発の違いが、スイッチの切り替え大事だよねっていうところと繋がります。
情報流通の3段階構造
情報流通の、これ情報流通構造って呼んでるんですけど、この3段階がすごく大事だと思っているんです。
- 局地的な熱狂:フォロワーとかファンとかが反応する。大抵はここで終わる。ファンにしか届かない。
- 教養的に広がる(イケてる情報):情報交換で広がる。ファンではない人も「あのYouTuberすごくいいことしてるね」という形で事象自体は届いていく。これは IMPAKTで言うとニュース性があるInverseかMostか。
- 情報がマス化する(キテる情報):行列、完売、100万再生、トレンド入りといった、話題になったという事象自体が取り上げられるケース。第3段階はマスメディアってやっぱりキテる情報が多いです。
すごく話題になったものってこの3段階を踏んでると思うんです。プランナーからしたら、2段階、3段階それぞれに何かこうプランニングをしてくとかマイルストーンを置いてくっていうことが重要。
PESOと情報流通構造の連動
(中略:ゾンビ臭の事例と3段階構造の連動)
ロードマップがありますよね。時系列でここで、PESO順に時系列にしてくっていうことも大事です。ローンチのタイミングは非常に重要。僕は72時間スケジュールというのをよく作るんですけど、72時間でどんなことをこのPESOでプロットしていくのか。そしてその1週間、2週間、1ヶ月をどういう風にやってくのかってことをプロットする。PESOを情報流通構造の面で見ていくってことも1つ重要。
PR思考のまとめと実践のヒント
マーケターのためのPRマインド4原則
- PRは同じを見つけるのが得意です。違いを見つける技術と同じを見つける技術。どうやったら手を結べるかなというようなところを探してくっていうのはPR思考のコツ。
- PRは第3者に語ってもらう。自分が言うのではなくて誰かに語られる。誰かっていうことが欲しいものは何かっていうことをまた思考を切り替える必要がある。
- PRはマルチコンテクスト。広告は一点突破。PRは料理しやすい素材に編集して渡す。その発想をマルチコンテクストでやってく。
- PRは流通型。投下するものと流通するものを分けて考える。PESOを立体的に、ファネルジャーニーにおけるところにフォーメーションとしてどう組むか。
企画者のためのワンポイント復習 6選
- 5W1Hを1個ずらしてみる。InverseやMostを作り出してみる。
- フォロワー数よりもActorの文脈を見直す。どんな文脈をまとってる人がいるかを見つけてみる。
- みんなが使いたくなる愛称って何だろう。世の中に出す前に、もうちょっと愛称っぽく呼べないかなって。最後の1個をもう1回キーワード化してみる。
- 制作スケジュール上ここがローンチだよねってことじゃなくて。この日だからこそこの企画が光るんだっていうような。最も賛成しやすい日を見つける。
- マルチコンテクスト。1つの魅力だけじゃなくて多数の魅力。多数のメディアに語られるにはどういう顔付きをしていくといいのか、どういうファクトを用意するといいのかっていう風に考える。
- コミュニケーション施策はもちろんアーンドはすごく大事。PESO全体を見て設計しましょうね。情報を流通させるという視点で。
推奨される学習リソース
今日お話ししたようなメソッドとかは、このPRX Studio Qのnoteに載ってるものも多いので、是非見てみてください。制作をお手伝いさせていただいた「あたりまえの作り方」という本も発売しております。あとですね、日経さんがやってるトキアカというサービス。PR思考を身につけるのに非常にお勧めです。日経新聞のニュースがクイズになっている。記者の目線というのがクイズを解いていくだけで身につきます。
Q&A:PR思考の具体的な磨き方と効果測定
池田:根本さんの話を聞くとやっぱりこのPR発想、PR思考っていうのはめちゃくちゃ重要。広告脳が染みついている人がPR思考に切り替えるには3年から5年かかる。このPR思考力をどのように磨くのかとなると、これは簡単じゃない。具体的なトレーニング法やお薦めの生活習慣はありますか?
根本:色々あると思います。ご自身のやりやすい方を見つけていただければと思うんですけど。やっぱりですね、今日の話から関連させると、もう騙されたと思ってPR IMPAKT®で分解してみるっていうのはめちゃくちゃお薦めなんですね。私も新入社員の時にひたすらPR IMPAKT®ニュースっていうのをやりました。
何かって言うと企業が取り上げられている記事をまず持ってきて。そこでもうチェックしてくんですね。これはInverseだからここが見出しになっている。Mostだからここ見出しになっているってことをまず分析していくんですね。自分で生み出すんじゃなくて。
そうするとこれ本当にInverseとMostないとニュースにならんやんってことが分かるんですよ、自分で。とか、これやっぱりPublicだから今取り上げられてるんだっていうものとか、ちょっと面白い言葉の使い方があるな。メディアの特徴だな、「なんとか活」多いな、とか。ただ、普段見ているメディアはそんなに変わらないと思います。一般的に皆さんが見ているもので良くて特殊なサイトとかはない。逆にそれを分析して見てるっていうのが、やっぱりこれはちょっと近道ないかもしれないんですけど。すごくお薦めではありますね。
池田:どのようにこの IMPAKTが生まれたのかというメソッドのところで、いろんな数あるニュースを分析していった時に、いくつかのパターンとか規則性とか法則みたいなやつをまとめたら IMPAKTに分類できましたっていう、抽象化をして濃縮果汁還元していったら IMPAKTにまとめられましたって話じゃないですか。
根本:そうなんです。
池田:だから論調を抽象化した結果としてこういうものがニュースになっているということは、自社が何かニュースになりたい時にそうなってなかったらニュースになんかならないっていうことを体に叩き込むしかないと。
根本:本当そうですね。
池田:(PR思考のトレーニングについて)簡単な魔法の杖とか近道なんかないと思うから、そんなものはないっていうことを知ることが1番の近道かも。
根本:それで言うとちょっとヒントというかこれは反則かもしれないけどAIっすね。やっぱAIで。PR IMPAKT®のフレームをプロンプトに入れて、今こういう素材があるんだけどPR IMPAKT®で出してねって言うと。要は何の文脈も考えてないけどPR IMPAKT®っぽくなる。
それは正直、10個あったら1個いいかもっていうのが出てくる可能性は結構ありますね。こことここ繋げ合わせれば企画になるじゃんとかはあるので。そういうものはうまく使える方は使ってもいいかなと思いますが。その際っていうかさ、本当にメディアと行動・対峙するって言った時にスカスカになってしまうとあれなんで。お薦めとしては今、訓練はしつつ、そういうものにスポットで頼る。そんな感じかなと思いますけども。
社内のPR思考ギャップの埋め方
池田:問題は、MARPSにそういった意識を持って学びに来た人たちが社内でこういった話をしようとした時に、まったくこの意識が共通化されていなくて、共通言語で会話ができないみたいな問題にぶち当たっていると思うんです。このPR思考だったりPRそのものに対する意識が低い。なにをしたら、「認識がずれている」「間違っている」みたいなところのギャップを埋められるのか。何か僕はこういうことやってますよっていうものってありますか。
根本:これも万能じゃないかもしれないですけど、やはりPR思考だと思っているんですよ。つまり他者の窓から見ることが大事なので、その分からないと言っている人の方に入る。そっちの相手が使っているKPI、相手が使っている言葉とPRの違いを言語化するというのがめちゃくちゃ大事だと思う。
例えばマーケティングとPRってどう違うのか。ブランディングとレピュテーションってどう違うのかとか。その相手が使っているものとPRの違いっていうのを言語化してあげて。あ、あなたこれ目指してるなら私ここやりますね。っていう風にやれるといいと思います。広告とPRの違いは、「違いを見つけること」と「同じを見つけること」ぐらい違うから。これどっちもやれた方がいいよね。って言ってこれ広告とPRが喧嘩しなくなるってことですね。
相手の窓から見た時のPRのポジションや違いを説明してあげるってのはめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。
池田:あの人は分かってねえなみたいな話で終わらせるんじゃなくって。その場合もまさにPR思考でこっちとあっちを使うわけ。あの人はこういう目線で見ているからこっちからはこういう話をあの向こうの立場に立ってしてあげよう、と。
根本:まさにそうですね。
池田:(広告畑の上司について)要は広告でPRを語ろうとするとか。即効性の問題だったり。あとはPRそのものの認知度の向上だったりとか。商品の売上そのものの貢献度みたいなものを持たせようとしちゃったりとか。なんかそこら辺もやっぱり共通言語作りっていうところがやっぱり絶対に必須っていうところなんですかね。
根本:そうですね。認知は追わないんですって言った時に、それで終わるとじゃあ何を追うの?となってしまうので。じゃあ最終的なKGIはなんですか?じゃあ中間KPIとしてPRはこうですかね?という風にその場で整理してあげられるかっていうのは大事だと思うんですよね。要はPRを、なんか敵だと思っていることがやっぱ多いんだと思う。分かんないからっていうのもあって。やっぱ味方だよっていう風にやるのがいいと思う。
PRはクレジットのつかない仕事ですって言ったことがあります。クレジットはメディアにあるし記者にあるから、僕はそこにこだわってないんです。と言った途端、クリエイターが「あ、そうだったの。じゃあ仲間じゃん」みたいになったみたいなのがあったりして。相手が何に対して壁を感じてるとかフラストレーションを感じてるかっていうところの違いを、やっぱり洞察したり聞いたりして対話するってことはすごい大事かなと思いますけどね。
PRの効果測定の考え方
池田:このPRにおける効果測定って基本はこのやり方だったり、こういう指標を追いかけるのが本筋だと思いますよっていうのって何か最後ヒントありますか。
根本:マーケティング文脈で語るかコーポレート文脈で語るかにもよるんですよね。マーケティングの講座だと思いますので。
まず広告換算についてはそのバルセロナ原則というもので、否定されていますよね。よくあるのはそのPRの指標でいくとやっぱりその、アウトカム、アウトプット、アクションという3つですよね。
アウトカムは、その意識変容とかその最終目的です。例えば日経イメージ調査とか、なかなか上がりづらいわけですよね。アウトプットはそれこそ露出、どういう風に語られたか。そして意図するメディアにどういう切り口で取り上げられたかという定性・定量。これアウトプットですよね。
で、そのために何をアクションしたか。例えばメディアの人に会いましたかもしれないし。これぐらいリリースを出しましたかもしれないし。そのアクションとの因果関係を押さえるのは難しいかもしれないが、いかにこの時の相関を取っておくかっていうところはまず大事なんだと思うんです。
ブランドと、レピュテーションの違いとかにも近いんですけど。MVVとかパーパスとかブランドパーパスを作った時にこれは自分がどうありたいかなんですよね。これをPRの手法にした時に、他者にどう語られたいかっていうのがPRの合わせ鏡になるわけですよ。
こういう風なミッションビジョンバリューありたい姿になれた時に世の中はあなたをどう語っているんですかという発話ベースの目標を決める。そういう風に語られてる時ってメディアはこうやって見出しにしますよねと。あなたのことを自動車会社と言わずモビリティカンパニーと言いますよねっていう風に語られ方の目標を設定する。
池田:意識変容・態度変容のために広告だけではなかなか難しい領域をPRが担ってレピュテーションそのものを作っていくことによってみたいな話であれば、やっぱり結局その効果の検証が簡単か難しいかではなくて。何を本質的に取るべきかで言うとやっぱり意識変容、態度変容指標が究極の指標であるべきっていうことですよね。
根本:そうですね。
池田:はい、ありがとうございました。ということで皆さんいかがだったでしょうか。最後に、やりたい人1万人、やる人100人、やり続ける人1人といういつもの自己啓発のセミナーで言ってることを今回の最後の締めにしたいんですが。
さっき全てのニュースを自分でIMPAKTで選別していくと言うのをやる人やらない人で多分1年2年経った時のPR思考力には相当雲泥の差が出るんじゃないかと思いましたので、是非皆さん、「ためになったな」だけじゃなくて、自分でできるようになるためにはそのトレーニングもしていっていただければと思います。
ということで今日は株式会社芽代表取締役の根本さんにPR思考のお話をしていただきました。根本さん改めて今日はありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。コメントもありがとうございます。ありがとうございました。
では皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。